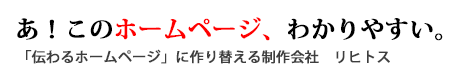クリニックのホームページ運営を担当されている院長先生、事務長様、広報担当者様の中には、日々の診療でお忙しい中、このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
- 「ブログが大切とは聞くが、具体的に何を書けばいいか分からない」
- 「集患につなげたいが、医療広告ガイドラインに違反するのが怖くて、当たり障りのないことしか書けない」
- 「書き始めたもののネタが尽きてしまい、更新が止まってしまった」
- 「そもそも、ブログを書く時間も余裕もない」
これらは、私たちがご支援する多くのクリニック様から寄せられる共通の悩みです。
しかし、これらの悩みは「正しい戦略」を知ることで、すべて解決できます。
この記事は、単なる「ブログネタ集」ではありません。
この記事の目的は、(1)患者さんとの信頼を築き、(2)SEO(検索エンジン最適化)で評価され、(3)法律を遵守する、という3つの目的を同時に達成するための「ブログ運営の戦略と実践マニュアル」をご提供することです。
この記事を最後までお読みいただければ、「何を書くべきか」という悩みから解放され、自信を持って患者さんの役に立つ情報発信ができるようになります。
目次
なぜ今、クリニックにブログが必要なのか? 4つのブログのメリット
まず、なぜ忙しい診療の合間を縫ってまでブログを運営する必要があるのでしょうか。
それは、ブログが他のどの広告媒体よりも優れた、4つのメリットを持っているからです。
【メリット1】「悩み検索」からの新規患者獲得

患者さんが医療機関を探すとき、検索行動は大きく2つに分かれます。
- 「指名検索」「地域名検索」:「〇〇クリニック」「△△市 内科」など、すでに来院の意思が固まっている検索。
- 「悩み検索」:「〇〇 痛い 原因」「△△ 治し方」「□□ 薬 副作用」など、まだ特定のクリニックを決めていない、症状や不安で検索している段階。
ホームページのトップページは「1」の受け皿にはなりますが、「2」の無数にある「悩み検索」のすべてに対応することはできません。
ブログは、この「悩み検索」の受け皿となるページを無限に増やすことができる最強のツールです。
「〇〇市 花粉症」 や「歯周病 予防策」 といった検索であなたのブログ記事が上位に表示されれば、まだ特定のクリニックを決めていない患者さんにとって最初の「専門家」として情報提供をすることができます。
これは、未来の患者さんを獲得する上で非常に大きなアドバンテージとなります。
【メリット2】患者さんとの信頼関係の構築

患者さんが医療機関を選ぶ上で、治療技術や設備と同じくらい重視しているのが「この先生は信頼できそうか」という点です。
特に初めてかかるクリニックに対しては、誰もが不安を抱えています。ブログは、その不安を来院前に和らげるための強力なツールとなります。
医師が自らの言葉で、治療に対する考え方、専門性、あるいはスタッフの人柄や院内の雰囲気を丁寧に発信することで、「ここなら安心して相談できそう」という信頼感を持ってもらえる可能性があります。
この「来院前の信頼構築」こそが、ブログにしかできない重要な役割です。
【メリット3】クリニックのブランディングと専門性の確立

特定の疾患や治療法について、専門性の高い記事を発信し続けることは、クリニックの「ブランディング」に直結します。
例えば、ある眼科が「子どもの近視治療」に関する専門的な記事を継続的に発信すれば、地域の保護者の中で「子どもの目のことなら、あのクリニック」という専門家としてのブランドが確立されます。
ブログを通じて一貫した情報を発信することは、他院との明確な差別化につながるのです。
【メリット4】採用活動(リクルート)への好影響

ブログは患者さんだけが見ているわけではありません。
院内の研修の様子や、院長の理念、スタッフの働く姿を発信することは、求職者にとっても重要な判断材料となります。
クリニックの価値観に共感する優秀な人材の確保にも繋がる、副次的ながら大きなメリットです。
書く前に必須!「医療広告ガイドライン」を理解する

ブログの戦略的な価値をご理解いただいたところで、次はいよいよ「何を書くか」です。
しかしその前に、クリニックのブログ運営における最大の障壁、「医療広告ガイドライン」について正しく理解する必要があります。
クリニックのブログは「広告」です
「これは広告ではなく、情報提供だ」というお考えもあるかもしれませんが、2018年の医療法改正により、その考えは通用しなくなりました。(参考:厚生労働省ホームページ『医療法における病院等の広告規制について』)
- 患者の受診を誘う意図(誘引性)があり
- クリニック名や医師名がわかる(特定性)がある
この2つの条件を満たすものは、ホームページやブログ、SNSであってもすべて「医療広告」とみなされ、ガイドラインの規制対象となります。
クリニックのブログは、これに該当するケースがほとんどです。
(参考:厚生労働省『医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)』)
知らないと危険!ガイドラインで禁止される4大表現
では、具体的に何が禁止されているのでしょうか。
これらはすべて、患者さんに誤った認識を与え、不利益を被ることを防ぐためのルールです。
特に注意すべき4つの項目をご紹介します。
- 虚偽・誇大広告:医学的にあり得ない表現(例:「必ず治る」「絶対安全な手術」)や、科学的根拠の乏しい情報、根拠を明示しない調査結果(例:「患者満足度99%」)は禁止されています。
- 比較優良広告:他の医療機関と比較して優れていると示す表現(例:「〇〇地域でNo.1の実績」「当院だけの最新治療」)や、「最高」「日本一」といった最上級の表現は、客観的な事実であったとしても原則禁止です。
- 患者さんの体験談:これが最も誤解の多い点です。患者さん個人の主観に基づく感想(例:「先生が優しかった」「痛くなかった」「すぐに良くなった」)を、内容に関わらず医療機関のウェブサイトに掲載することは禁止されています。口コミサイトからの転載や、スタッフによる紹介も同様にNGです。
- ビフォーアフター写真:治療前後の写真(ビフォーアフター写真)は、患者さんを誤認させるおそれがあるものとして、原則禁止されています。特に、写真に加工や修正を加えることは虚偽広告にも該当します。ただし、厚労省『事例解説書(第5版)』では、各写真ごとに術式・回数・費用・主なリスク/副作用などの詳細情報を明記する改善例が示されています。実務上は違反リスクが高いため、症例解説で客観情報を丁寧に提示する運用を推奨します。
医療広告ガイドラインでの禁止表現と「安全な」言い換え例
ここまでお読みいただいた方の中には「禁止ばかりで、何も書けない」と不安になられた方もいらっしゃるかもしれません。
ご安心ください。
ガイドラインが求めているのは、「主観的・感情的な表現」を避け、「客観的・事実ベースの表現」に徹することです。
現場の担当者様が最も知りたい「じゃあ、どう書けばいいのか?」にお答えするため、具体的なNG表現と安全なOK表現の「言い換え」を以下の表にまとめました。
| 禁止カテゴリ | NG表現の具体例(主観・誇張) | OKな言い換え例(客観・事実) |
| 誇大広告 | 「この治療で必ずシミが消えます」 | 「この治療は、〇〇というメカニズムでシミの改善を目指すものです。効果には個人差があります」 |
| 「絶対安全な手術です」 | 「あらゆる手術にはリスクが伴います。 当院の手術では、〇〇や△△といったリスク・副作用の可能性があります。詳しくは診察時にお尋ねください」 | |
| 「満足度99%」 | 「令和〇年〇月実施の院内アンケート(回答者数:XX名)では、XX%の方から『満足』との回答をいただきました」 (※客観的な調査の事実として) | |
| 比較優良広告 | 「〇〇地域でNo.1のクリニック」 | 「当院は〇〇(地名)で〇〇年以上にわたり、地域の皆様のかかりつけ医として医療に貢献してまいりました」 |
| 「当院だけの最新治療」 | 「当院では、〇〇学会の診療ガイドラインで推奨されている〇〇治療法(〇〇社製)を導入しています」 | |
| 体験談 | 「患者A様:全く痛くありませんでした!」 | (掲載不可。代替案として、クリニックの「取り組み」という事実を記載) →「治療時の痛みを軽減するため、当院では〇〇麻酔や冷却装置を使用し、患者さんのご負担を減らす工夫をしています」 |
| ビフォーアフター | (治療前後の写真2枚を並べて掲載) | (原則掲載不可。代替案として、「症例解説」として客観的情報を記載) →「症例:40代女性。〇〇の症状。治療法:〇〇。治療期間:Xヶ月。標準的な費用:X円。主なリスク:〇〇」 |
「限定解除」を正しく理解する
「限定解除」とは、特定の要件を満たすことで、通常は広告できない専門的な情報(自由診療の詳細、リスク、副作用など)も掲載できるルールです。
これは「法律の抜け道」では決してありません。
むしろ逆で、「患者さんが正しい判断をするために必要な情報を、良いことも悪いことも含めて、すべて隠さず提供する」という誠実な姿勢を求めるルールです。
限定解除の主な要件
- 患者さんが自ら情報を求めてアクセスするブログなどであること。
- 問い合わせ先(電話番号、メールアドレスなど)が明記されていること。
- 【自由診療の場合】治療内容、標準的な費用、主なリスク、副作用などを詳細に明記すること。
結論として、リスクや費用を隠さずに正確に記載することは、ガイドライン遵守と患者さんの信頼獲得の両面で、非常に重要なポイントとなります。
SEOで勝つ医療記事の鍵「E-E-A-T」と「著者情報」

ここでは、もう一つの壁である「SEOの壁」、すなわちGoogleに「この記事は信頼できる」と評価してもらうための戦略を解説します。
医療は最難関の「YMYL」ジャンル
Googleは、人の健康、生命、財産に大きな影響を与える可能性のある情報分野を「YMYL(Your Money or Your Life)」と呼び、その評価基準を全ジャンルの中で最も厳しく設定しています。
医療・健康情報は、まさにYMYLの中核です。
このYMYL分野でGoogleから高い評価を得るために、絶対に満たさなければならない基準が「E-E-A-T」です。
E-E-A-Tとは? 医療ブログにおける意味
E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取ったもので、Googleがコンテンツの品質を評価するための指針です。
- Experience(経験): 著者がそのテーマについて「実体験」を持っているか。
- 医療ブログでは: 医師や看護師が、実際に患者さんを診察・治療した「臨床経験」に基づく一次情報。
- Expertise(専門性): 著者がそのテーマの「専門家」であるか。
- 医療ブログでは: 医師免許、歯科医師免許、専門医資格など、医学的知識を持つこと。
- Authoritativeness(権威性): 著者やサイトが、その分野の「権威」として認められているか。
- 医療ブログでは: 所属学会、論文、学会発表、書籍執筆など、第三者(アカデミア)からの客観的な評価。
- Trustworthiness(信頼性): 記事とサイトが「信頼」できるか(最も重要)。
- 医療ブログでは: 情報が正確で科学的根拠(EBM)に基づいていること、サイトが安全(SSL化)であること、運営者情報(クリニック情報)が透明であること。
【最重要】E-E-A-T対策の「特効薬」=著者(監修者)プロフィールの徹底
E-E-A-Tという言葉は抽象的に聞こえますが、Googleと読者に対して、上記のE-E-A-Tを最も簡単に示す方法があります。
それが、記事ごとに「誰が書いたか(監修したか)」を明記することです。
一般のライターが書いた記事よりも、医師免許を持つ院長が監修した記事の方が「専門性」と「信頼性」が高いのは明白です。
Googleはこの「誰が」を非常に重要視しています。
ここで、「医療広告ガイドライン」と「E-E-A-T」が、同じゴールを目指していることにお気づきでしょうか。
- ガイドラインは「誇大広告や体験談を禁じ、客観的な事実」を求めます。
- E-E-A-Tは「専門家による科学的根拠に基づいた情報」を求めます。
つまり、E-E-A-Tを高める努力(特に、医師が監修し、EBMに基づいた正確な記事を書くこと)は、そのまま医療広告ガイドラインの遵守に直結するのです。
この2つは対立するものではなく、「患者さんからの信頼」という一点において、完璧に両立するものです。
E-E-A-Tを高める具体的なアクション
E-E-A-Tの4つの要素を、あなたのブログで具体的にどのように高めるかを表にまとめました。
| E-E-A-T要素 | 医療ブログでの具体的な実践方法 |
| Experience (経験) | 医師やスタッフが臨床で実際に経験したこと、患者さんからよく受ける質問を基に記事を作成する(※個人が特定できないよう一般化・抽象化する)。 |
| Expertise (専門性) | 医師・歯科医師が自ら執筆、または最低でも必ず監修する。記事内に「この記事は医師〇〇が監修しました」と明確に記載する。 |
| Authoritativeness (権威性) | 記事の末尾や別ページに、詳細な著者(監修者)プロフィールを掲載する。(↓次項で詳述) 関連する学会や公的機関(厚生労働省、eJIM1 など)の一次情報を引用・リンクし、情報の根拠を明確にする。 |
| Trustworthiness (信頼性) | 科学的根拠(EBM)に基づかない情報(例:安易な「〇〇で免疫が上がる」等の健康食品情報)は書かない。 治療法を解説する際は、メリットだけでなくリスク、副作用、費用も必ず併記する(※「限定解除」の要件でもあります)。 運営者情報(クリニック名、住所、電話番号)を明記し、サイトをSSL化(https://)に対応させる。 |
【テンプレート】そのまま使える「監修者プロフィール」の例
E-E-A-T対策の核となる「監修者プロフィール」のテンプレートです。
参考にしてみてください。
この記事の監修者
[(可能であれば医師の顔写真)]
氏名: 〇〇 〇〇(医療法人〇〇会 〇〇クリニック 院長)
ご挨拶:
(例:〇〇地域の皆様の「かかりつけ医」として、お一人おひとりの健康に寄り添った医療を心がけています。このブログでは、医学的根拠に基づいた正確で分かりやすい情報を発信し、皆様の健康維持のお役に立てれば幸いです。)
経歴:
- 20XX年 〇〇大学医学部 卒業
- 20XX年 〇〇大学病院 〇〇科 勤務
- 20XX年 〇〇医療センター 〇〇科 医長
- 20XX年 〇〇クリニック 開院
保有資格・所属学会:
- 医学博士
- 日本内科学会 総合内科専門医
- 日本消化器病学会 消化器病専門医
- 日本〇〇学会 〇〇専門医
【ネタ切れ解消】2つの目的別「すぐに書ける」ブログネタ23選

「法律」「SEO」のルールを踏まえ、いよいよ具体的に「何を書くか」のネタをご紹介します。
ネタが尽きてしまう原因は、多くの場合「誰に」向けて書くかが定まっていないことです。
クリニックブログのネタは、読者と目的に合わせて、大きく以下の2つの「バケット(分類)」に分けて考えるとうまくいきます。
【SEO対策】「悩み検索」に応えるお役立ちネタ
目的: 潜在的な患者さんに「専門家」として認知され、検索流入を獲得する。
ターゲット: 症状や治療法について、能動的に情報を調べている人。
- 疾患・症状の解説
- 例:「その頭痛、大丈夫? 危険な頭痛の見分け方と片頭痛の最新治療」
- 例:「子どもの虫歯、進行度別の治療法と予防法を歯科医が解説」
- 治療法・検査の解説
- 例:「当院の〇〇(最新機器)を導入しました。この検査で何が分かりますか?」
- 例:「ピルの種類と特徴、副作用について医師が解説」
- 例:「歯ぎしりの原因とマウスピース(ナイトガード)による治療法」
- 予防・セルフケア
- 例:「今日からできる! 歯周病のセルフチェックと正しい歯磨き法」
- 例:「花粉症シーズンを乗り切るための3つのセルフケア対策」
- 例:「虫歯予防に効果的な食べ物・飲み物」
- 患者さんからよくある質問(FAQ)
- 例:「『ワクチンの副反応が心配』…患者さんからのご質問にお答えします」
- 例:「子どもの歯のケア、フッ素はいつから? 歯科医が回答」
- 季節性のトピック
- 例:「冬に流行する感染症(インフルエンザ・RS)の予防と受診の目安」
- 例:「夏に注意したい子どもの『とびひ』とは? 皮膚科医が解説」
- 例:「秋のシミ取りシーズン到来。〇〇治療のメリット・デメリット」
【信頼構築】クリニックの「人柄」を伝えるブランディングネタ
目的: 来院前の不安を取り除き、「このクリニックに行きたい」と思ってもらう。
ターゲット: すでにクリニックの存在を知り、受診を検討・比較している人。
- 院長の理念・想い
- 例:「私がこの〇〇の地で開業した理由」
- 例:「〇〇治療(例:無痛治療)に私たちが込める想い」
- スタッフ紹介
- 例:「スタッフ紹介:〇〇(看護師)の自己紹介と患者さんへのメッセージ」
- 例:「受付カウンセラー募集のお知らせ(私たちが大切にしていること)」
- 院内の様子・こだわり
- 例:「当院の感染対策の裏側、ここまで徹底しています」
- 例:「リラックスしていただくための待合室のこだわり〇選(BGM、香りなど)」
- 研修・勉強会の報告
- 例:「先日の院内勉強会レポート:〇〇(新薬)について学びました」
- 例:「〇〇学会に参加してきました(最新の知見を診療に活かします)」
- クリニックからのお知らせ(背景と共に)
- 例:「〇月からの診療時間変更のお知らせと、その理由について」
- 例:「〇〇(治療)のキャンペーンのお知らせ(11月のオススメ治療)」
診療科別 ブログネタのヒント
さらに具体的に、診療科別のネタのヒントをまとめました。
| 診療科 | SEO対策ネタ(悩み解決) | 信頼構築ネタ(人柄・雰囲気) |
| 皮膚科 | 「ニキビ跡の種類別治療法(クレーター・色素沈着)」 | 「当院おすすめの日焼け止め3選と正しい塗り方」 |
| 歯科 | 「インプラントとブリッジ、どちらを選ぶべき?メリット・デメリット比較」 | 「歯科衛生士が教える! お子さんの仕上げ磨きのコツ」 |
| 内科 | 「高血圧の薬は一度始めたらやめられない? 医師が解説します」 | 「院長が健康のために実践している3つの習慣(食事・運動)」 |
| 整形外科 | 「その『ぎっくり腰』、どう対処する? 安静は間違い?」 | 「理学療法士紹介:リハビリテーションにかける想い」 |
| 耳鼻咽喉科 | 「子どもの中耳炎、なぜ繰り返す? 治療と家庭でのケア」 | 「ネブライザー(吸入器)の上手な使い方と清掃方法」 |
| 眼科 | 「ドライアイの目薬、選び方のポイントと正しい差し方」 | 「最新のOCT(光干渉断層計)を導入しました」 |
もうネタ切れしない! ブログネタの「見つけ方」5つの習慣
先ほどネタをリストアップしましたが、最も重要なのは「ネタを継続的に生み出す仕組み」です。
ネタ切れを防ぐための5つの習慣をご紹介します。
- 患者さんとの会話を「メモ」する:これが最強のネタの源泉です。患者さんが診察室で実際に口にした疑問や不安(例:「この薬、いつまで飲むの?」「この治療は保険がきくの?」)は、そのまま他の患者さんや、検索している人の「悩み」そのものです。
- 関連キーワードを「調査」する:「aramakijake.jp」 や「ラッコキーワード」などの無料ツールで、あなたの「診療科名」や「疾患名」を入力してみてください。検索ユーザーがどのような言葉を組み合わせて検索しているか(サジェストキーワード)が一覧で表示されます。
- SNSやYahoo!知恵袋を「観察」する:X(旧Twitter)やYahoo!知恵袋で、あなたの診療科名や関連する疾患名を検索します。そこには、患者さんのリアルな言葉での「悩み」や「誤解」が溢れています。
- 過去記事を「リライト」する:ネタ切れした時は、新しい記事を書くことだけが選択肢ではありません。1年前に書いた記事は、情報が古くなっている可能性があります。最新のガイドラインや治療法に合わせて情報を追記・修正(アップデート)するだけで、Googleの評価も上がる、立派な新しい記事になります 。
- 他のスタッフに「ヒアリング」する:院長先生(医師)の視点だけでなく、看護師、受付スタッフ、医療事務など、異なる立場からネタを集めましょう。「最近、受付でよく聞かれることは?」「看護師として患者さんにもっと知っておいてほしいことは?」といった質問が、新しい切り口のネタにつながります。
患者さんの心に届く「書き方」5つのコツ
素晴らしいネタが決まっても、「書き方」が専門的すぎると患者さんには届きません。
専門家として、やさしく伝えるための5つの技術をご紹介します。
- ターゲット(読者)を1人に絞る:「患者さん全員」に向けて書くと、誰の心にも響かない、総花的でぼんやりとした記事になります。「〇〇(疾患名)と診断されて不安になっている30代の女性」のように、たった一人の読者をイメージし、その人に優しく語りかけるように書きます 4。
- 専門用語を「翻訳」する:「EBM」「MEO」「〇〇術式」のような専門用語は使わないか、必ず「〇〇(例:内視鏡)とは、胃の中を直接見るカメラのことです」のように、中学生でも分かる言葉で解説を加えます 4。
- 記事のテーマは「1記事1テーマ」を徹底する:「花粉症」について書くなら、「花粉症の症状と対策」だけに絞ります。そこで「アレルギー性鼻炎」や「喘息」の話まで広げすぎると、読者は混乱し、Googleの評価(専門性)も分散してしまいます 4。
- イラストや画像、表を活用する:文字だけの記事は、体調が優れない患者さんにとっては読むのが苦痛です。図解、院内の写真、そしてこの記事で使っているような「比較表」を使い、視覚的に分かりやすくする工夫が不可欠です 4。
- 記事の最後は「監修者情報」で締めくくる:ご紹介した「監修者プロフィール」を必ず記事の最後に配置し、「この記事は専門家である私たちが責任を持って発信しています」という姿勢を明確に示します。
まとめ

クリニックのブログ運営は、「SEO(集患)」と「医療広告ガイドライン(法律)」という2つの側面を同時に満たす、高度な情報発信戦略です。
一見、難しく感じるかもしれませんが、本質は驚くほどシンプルです。
それは、「患者さんに対して、正確で、誠実な情報を、専門家として分かりやすく提供すること」に他なりません。
ガイドラインを「制限」と捉えるのではなく、「患者さんとの信頼を築くためのルール」と捉え直してください。
そして、GoogleのE-E-A-Tは、その「信頼」を正しく評価するための仕組みです。
「何を書くか」に迷ったら、この記事で紹介した2つのバケット(「悩み解決ネタ」「信頼構築ネタ」)を思い出してください。
まずは月1本からでも構いません。
あなたのクリニックの専門性と温かい想いが伝わる記事を発信し、未来の患者さんとの大切な信頼関係を築いていきましょう。
お問い合わせはこちら
当社ではホームページの制作と管理をおこなっています。
ホームページの管理費は月額換算で3,300円です(年払い税込39,600円)。
ホームページの管理をさせて頂いているお客様には、ブログ記事の書き方に関するご相談なども受けております。
これから作るホームページの制作、現在お持ちのホームページのリニューアルや保守管理に関してなど、ホームページに関することはなんでもお気軽にご相談ください。