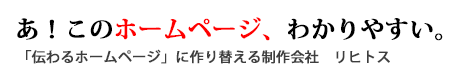院長先生、医院のスタッフ様の中には「医院のブログ、何を書けばいいんだろう…」と頭を悩ませている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「ブログを始めたけれどネタが続かない」「そもそも、本当にブログが集患につながるのか実感が持てない」――。
そうしたお悩みは、ブログ運営を担当される多くの歯科医院様が共通して抱えているものです。
本記事は、そうしたお悩みを解決するためのブログのネタの探し方、Googleなどの検索エンジンに「専門性の高い、信頼できる医院だ」と評価される方法、さらにはブログを読んだ患者さんから「ぜひこの先生に診てもらいたい」と選ばれるなど、「資産になるブログ」の作り方をわかりやすくご説明したいと思います。
目次
なぜ今、歯科医院のブログが「集患」に必須なのか?

歯科医院のホームページをすでにお持ちの先生も多いと思います。
では、なぜわざわざ手間のかかるブログを書く必要があるのでしょうか。
それは、静的なHPだけでは届かない患者さんに、医院を見つけてもらうためです。
ブログの最大の目的は「問い合わせや来院者を増やす」ことにあります。
患者さんが歯医者さんを探す時、どう検索するか想像してみましょう。
多くの場合、「医院名」で直接検索するのではなく、「〇〇市(地域名) 親知らず」「△△駅 歯石取り」といった「地域名+症状・治療内容」で検索します。
医院のトップページだけで、これら無数の「お悩みキーワード」すべてに対応するのは不可能です。
ブログこそが、これらの「地域名+お悩み」キーワードの受け皿となります。
例えば、「〇〇市の親知らずでお悩みの方へ」といったブログ記事を1本公開すれば、それが医院のHPへの「新しい入り口」となります。
関連情報がサイト内に蓄積されることで、Googleのクローラー(ロボット)もサイトを巡回しやすくなり、結果として検索上位に表示されやすくなるのです。
近年はSNSも普及していますが、情報は流れてしまいがちです。
一方、ブログ記事は一度書けばインターネット上に残り続け、医院の代わりに「専門知識」と「人柄」を患者さんに伝え続ける「資産」になってくれるのです。
歯科医院ブログの「絶対的ルール」YMYLとE-E-A-Tとは?
「よし、じゃあ早速記事を書こう!」と、その前に。
歯科医院のブログ運営には、他の業種にはない「絶対的なルール」が存在します。
歯科医院は「YMYL」領域である
YMYLとは "Your Money Your Life" の略で、Googleが定義する「人々のお金や健康、人生に大きな影響を与える可能性のある」情報分野を指します 。
医療・健康情報を扱う歯科医院のウェブサイトは、まさにこのYMYLのど真ん中です 。
Googleは、YMYL領域の情報の品質を極めて厳格に評価します。
なぜなら、もし誤った情報が発信されれば、ユーザーの健康に深刻な損害を与える可能性があるからです 。
YMYL領域のポイント「E-E-A-T」

GoogleがYMYL領域の品質評価で最重要視するのが「E-E-A-T」という基準です。
E-E-A-Tとは、以下の4つの頭文字を取ったものです 。
- E (Experience - 経験): コンテンツ作成者が、そのトピックについて実際の経験(例:診療経験)を持っているか。
- E (Expertise - 専門性): 作成者が、そのトピックの専門知識やスキル(例:歯科医師免許)を持っているか。
- A (Authoritativeness - 権威性): 作成者やウェブサイトが、その分野の権威(例:専門医資格、学会)として広く認識されているか。
- T (Trustworthiness - 信頼性): ページがどれだけ信頼できるか。正確で、正直で、安全か。
E-E-A-Tの中で最も重要なのは「信頼性(T)」
Googleは、2022年12月の更新で「経験(E)」を追加しましたが、同時にこの4つの中で「信頼性 (T)」が最も重要であり、他のE-E-A(経験・専門性・権威性)が、この信頼性を支える土台である、という考え方を明確に示しました 。
歯科医院ブログの「本当の役割」
ここで非常に重要な点があります。
院長先生や歯科衛生士さんは、国家資格を持ち、日々の診療経験があるため、当然ながら「経験(E)」「専門性(E)」「権威性(A)」を持っています。
しかし、Googleは「ドクターが専門家だからといって、そのクリニックのウェブサイトが自動的にE-E-A-Tを獲得することはない」という立場です 。
つまり、先生方の頭の中にある「現実のE-E-A」を、Googleのロボットが読み取れる「デジタルのE-E-A-T」に変換・翻訳する作業が必要です。
歯科医院ブログの本当の役割とは、この「翻訳作業」そのものなのです。
単なる情報発信ではなく、医院の「信頼性(T)」をデジタル上で証明するための「証拠作り」がブログ運営の核心です。
【最重要】ブログでE-E-A-Tを高める5つの具体策

では、どうすれば先生方の「現実のE-E-A」を「デジタルのE-E-A-T」に変換できるのでしょうか。
今すぐできる5つの具体策をご紹介します。
1. 「誰が書いたか」を全記事に明記する(著者・監修者プロフィール)
Googleは「誰がその情報を発信しているか」を非常に重視します。
匿名の記事や「スタッフA」といった表記では、専門家が書いた証拠にならず、信頼性は低いと評価される可能性があります。
対策: できればブログ記事に、記事の執筆者(または監修者)の情報を必ず掲載してください。
掲載すべき項目:
- 氏名
- (できれば)顔写真
- 役職(院長、歯科医師、歯科衛生士など)
- 簡単な経歴(出身大学、勤務歴など)
- 保有資格(下記参照)
2. 「権威性」を示す資格・所属学会を明記する
院長先生やスタッフさんがお持ちの「専門医」「認定医」資格は、「権威性(A)」の強力な証拠です。
これらをプロフィール欄や医院紹介ページに、正式名称で記載しましょう。
対策(記載例):
- 公益社団法人 日本口腔外科学会 口腔外科専門医
- 公益社団法人 日本口腔インプラント学会 口腔インプラント専門医
- 日本障害者歯科学会 障害者歯科専門医
- 所属学会(日本歯周病学会、日本小児歯科学会 など)
3. 院長の「経験(E)」を語る(学会参加、日々の気づき)
2022年にE-E-A-Tへ新しく追加された「経験(E)」 は、単なる経歴(専門性)ではなく、「実際に体験したこと」を指します 。
一般的な「虫歯とは?」という解説記事は、極論すれば競合医院も書くことができます。
しかし、「最近、当院でインプラント治療を受けられた50代の患者様から、こんなご質問をいただきました」といった具体的な「診療体験」 は、その医院にしか書けない貴重な一次情報です。
これこそが、Googleが求める「経験(E)」の核心です。
日々の患者さんとのやり取り や、学会・勉強会への参加レポート は、専門性をアピールする絶好の「経験」記事となります。
4. 医院の「信頼性(T)」を裏付ける情報を公開する
患者さんは「この医院は本当に信頼できるか?」を見ています。
対策: 医院の理念、開院の歴史、導入している最新設備(滅菌体制など)の紹介、スタッフの顔が見える院内紹介 など、医院の透明性を高める情報を積極的に公開しましょう。
5. 引用元は「一次情報・公式情報」を徹底する
記事の信頼性を担保するため、情報の出典(ソース)は極めて重要です。
記事内で健康情報や統計に触れる際は、必ず「公式情報・一次情報」を引用し、引用元リンクを明記しましょう。
信頼できる引用元(OK例):
- 厚生労働省(例:歯科疾患実態調査)
- e-ヘルスネット(厚生労働省)
- 日本歯科医師会
- 各種専門学会(例:日本口腔外科学会)
信頼できない引用元(NG例):
- 匿名の個人ブログ、まとめサイト
- 出典が不明な健康情報サイト
- (※新聞やテレビの情報も、元の研究論文を確認しない限り一次情報ではありません)
ネタに困らない!歯科医院ブログの「鉄板ネタ」7選
E-E-A-Tの重要性をご理解いただいたところで、いよいよ「何を書くか」の具体的なネタをご紹介します。
【ブログのネタ1】:患者さんの「よくある質問・お悩み」に答える記事
戦略: 医院の「経験(E)」をアピールする最強のトピックです。日々の診療で患者さんからよく聞かれる質問 や、最近多い症状 こそが、最高のネタになります。
記事ネタの例:
- 「歯石取りって痛いですか? どのくらいの頻度で通えばいいの?」
- 「親知らずは、やっぱり抜かないとダメなのでしょうか?」
- 「子どもの歯並び、いつから気をつければいいですか?」
- 「電動歯ブラシと手磨き、結局どっちがいいの?」
【ブログのネタ2】専門的な「治療内容」をやさしく解説する記事
戦略: 「専門性(E)」をアピールし、治療への不安を取り除きます。専門用語を避け、患者さんが理解できる言葉で解説するのがコツです。
記事ネタの例:
- インプラント、入れ歯、ブリッジの違いとメリット・デメリット
- セラミック治療の種類と選び方(ジルコニア、e-maxなど)
- 当院の「痛みに配慮した」虫歯治療のステップ
【表の活用】:視覚的にわかりやすく比較する (例:ホワイトニングの種類別比較表) 患者さんは「ホワイトニング」に興味があっても、種類が多くて違いが分かりません。文字で説明するより、表で比較した方が直感的に理解できます。
表:ホワイトニングの種類別メリット・デメリット比較
| 比較項目 | オフィスホワイトニング | ホームホワイトニング | デュアルホワイトニング |
| 施術場所 | 歯科医院 | ご自宅 | 歯科医院+ご自宅 |
| 白さを実感するまで | 1回〜(即効性◎) | 約2週間〜(持続性◎) | 最も早い |
| 費用相場 (目安) | 2万~5万円 | 2万~4万円 | 5万~8万円 |
| 主な特徴 | 専門家が施術。忙しい方に。 | 後戻りしにくい。白さが長持ち。 | 短期間で理想の白さに。 |
| 注意点(リスク) | 一時的に知覚過敏が出やすい | 毎日続ける手間がかかる | 費用が最も高額になる |
【ブログのネタ3】安心を届ける「医院・スタッフ」紹介記事
戦略: 「信頼性(T)」と「経験(E)」を構築します。患者さんは「どんな人が」治療するのかを非常に気にしています。
記事ネタの例:
- 院長が歯科医師を目指した理由、治療にかける想い
- 新人歯科衛生士の紹介「〇〇さん(写真付き)はこんな人です!」
- 医院の感染対策(滅菌設備)へのこだわり、院内ツアー
- (※スタッフのプライベートな日常を載せる場合は、医院の「親しみやすさ」には繋がりますが、GoogleのE-E-A-T評価(専門性)には直結しにくい点も理解しておきましょう)
【ブログのネタ4】地域密着型の「ローカルSEO」記事
戦略: 「地域名+お悩み」 で検索する、来院確度の高い患者さんをピンポイントで狙います。YMYLとローカルSEOの相乗効果を最大化します。
記事ネタの例:
- 「〇〇市(駅)で小児歯科をお探しのお父様・お母様へ」
- 「〇〇小学校の歯科検診を担当しました(所感と注意点)」
- 「当院から△△(近隣の大型スーパー)へのアクセスと駐車場のご案内」
【ブログのネタ5】信頼できる「統計・公的情報」に基づく知識記事
戦略: 医院の「権威性(A)」と「信頼性(T)」を高めます。公的データを引用し、それに医院としての「専門的な解釈」を加えることで、オリジナルなE-E-A-Tコンテンツを作成します。
記事ネタの例:
- (最新データ活用例)
- ネタ: 厚生労働省「令和6年歯科疾患実態調査」の最新結果 。
- 記事タイトル案: 「速報!8020達成者がついに6割超え(61.5%) 。〇〇市で健康寿命を延ばすために当院ができること」
- (e-ヘルスネット活用例)
- ネタ: e-ヘルスネット「口腔の健康状態と全身的な健康状態の関連」 。
- 記事タイトル案: 「歯周病が糖尿病や心疾患と関連? 厚労省e-ヘルスネットに学ぶ『お口と全身の深い関係』」
【ブログのネタ6】セルフケアと「予防歯科」を啓発する記事
戦略: 患者さんの健康意識を高め、定期検診の重要性を伝えます。歯科衛生士さんが執筆者・監修者として「専門性(E)」を発揮するのに最適なトピックです。
記事ネタの例:
- 歯科衛生士が教える!「デンタルフロス」と「歯間ブラシ」の正しい使い分け
- フッ素塗布はなぜ虫歯予防に必要なのか?(セルフケアとの違い)
- 食事も重要!歯に良い食べ物、悪い食べ物
【ブログのネタ7】学会・勉強会の「参加レポート」記事
戦略: 「専門性(E)」と「経験(E)」を同時にアピールします。医院が常に最新の知識を学んでいる姿勢は、患者さんに大きな安心感を与えます。
記事ネタの例:
- 「先日、〇〇(学会名)に参加し、最新のインプラント技術を学んできました」
- 「院内勉強会で『最新の歯周病治療』について学びました」
書く前に確認!医療広告ガイドラインの必須知識
E-E-A-Tを高めることは重要ですが、同時に「法律」も守らなくてはなりません。
それが「医療広告ガイドライン」です。
ブログも、患者さんを誘引する目的がある限り「広告」とみなされます。
特に注意が必要なのが、患者さんに効果を訴求しやすい「ビフォーアフター写真(症例写真)」です 。
「ビフォーアフター写真」掲載の必須ルール
症例写真の掲載は禁止されていませんが、「限定解除要件」という厳しいルールを満たす必要があります 。
一見すると、リスクや費用を明記することは医院に不利に見えるかもしれません。
しかし、E-E-A-Tの観点では、良いこと(メリット)だけでなく、リスクや費用を正直に開示する誠実な姿勢こそが、Googleと患者さんからの「信頼性(T)」 を獲得する最大の鍵となります。
医療広告ガイドラインを守ることは、最強のE-E-A-T(信頼性)対策です。
リスクを恐れず、誠実に情報を併記しましょう。
【表の活用】:症例写真の「必須4項目」チェックリスト 症例写真を載せる際は、その写真(症例)ごとに、以下の4項目を分かりやすく(※小さすぎる文字はNG)併記する必要があります 。
| 必須項目 | 記載内容の具体例 |
| 1. 治療内容 | (例:セラミッククラウン(ジルコニア) 上顎前歯2本) |
| 2. 治療期間・回数 | (例:期間 約1.5ヶ月、通院4回) |
| 3. 費用 (自由診療の場合) | (例:自由診療 セラミッククラウン 1本 150,000円(税込)) |
| 4. 主なリスク・副作用 | (例:一時的に歯がしみる知覚過敏が起こることがあります。また、強い歯ぎしり等により稀に破損する場合があります) |
患者さんに伝わる「やさしい記事」を書くポイント
ネタが決まり、ルールも学びました。
最後に、どう書けば患者さんの心に響くか、具体的な「書き方」のコツをお伝えします。
【ポイント1】専門用語を「患者さんの言葉」に翻訳する
先生方にとっては常識でも、患者さんには伝わりません。「専門用語を使わない」 ことを徹底しましょう。
- (例)× 補綴治療 → 〇 詰め物・被せ物
- (例)× う蝕 → 〇 虫歯
- (例)× 歯周組織 → 〇 歯を支える歯ぐきや骨
【ポイント2】記事構成テンプレート「SDS法」を活用する
ブログは「結論ファースト」が読みやすさの鍵です。
説得型の「PREP法」 もありますが、まずはニュース記事のように分かりやすい「SDS法」 がおすすめです。
SDS法とは (Summary → Details → Summary)
- S (概要): 記事の「結論・要点」を最初に伝えます。
- D (詳細): 結論に至る「理由・具体例・詳細」を解説します。
- S (概要): 最後に、もう一度「結論・要点」をまとめて念を押します。
この構成は、忙しい患者さんが「この記事に自分の知りたい答えがあるか」を瞬時に判断でき、記憶にも残りやすいメリットがあります 。
【ポイント3】写真やイラストを活用し、文章を詰め込みすぎない
文章ばかりのページは読まれません。
院内や設備の写真、治療を解説するイラストなどを適宜挿入し、視覚的に分かりやすくしましょう。 (※ただし、治療中の出血などが伴うような写真は、患者さんに不快感を与える可能性があるため避けた方が良いかもしれません)
【ポイント4】記事の最後は必ず「行動」を促す
記事を読んで「勉強になった」で終わらせては、集患につながりません。
記事を読み終えた患者さんの「不安」や「悩み」を受け止める、次のステップを用意しましょう。
- (例)「親知らずが気になる方は、まずはお気軽に無料相談へお越しください」
- (例)「ご予約・お問い合わせはこちらのフォームからどうぞ」(予約フォームへのリンクを設置)
まとめ

本記事では、「歯科医院のブログに何を書くか」というテーマで、SEOの基本戦略からE-E-A-Tの高め方、具体的な7つのトピック、そして医療広告ガイドラインの注意点まで、出来るだけわかりやすくお伝えしました。
ブログ運営は、決して簡単な作業ではありません。
しかし、E-E-A-T(特に先生方の「経験」と「専門性」)を意識し、患者さんに寄り添った記事を一つひとつ丁寧に発信していくこと は、GoogleからのSEO評価を高めるだけでなく、それ以上に患者さんとの「信頼関係」を築く、何物にも代えがたい「資産」となります。
まずは先生ご自身の「経験」が活きる、「患者さんからよく聞かれる質問」 への回答から始めてみませんか。
先生方の素晴らしい知識と経験が、ブログを通じて多くの患者さんに届くことを心から応援しています。
お問い合わせはこちら
当社ではホームページの制作と管理をおこなっています。
ホームページの管理費は月額換算で3,300円です(年払い税込39,600円)。
ホームページの管理をさせて頂いているお客様には、ブログ記事の書き方に関するご相談なども受けております。
これから作るホームページの制作、現在お持ちのホームページのリニューアルや保守管理に関してなど、ホームページに関することはなんでもお気軽にご相談ください。