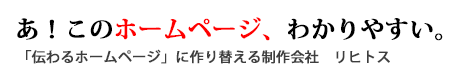インテリアコーディネーターとして活動を始めた、あるいはすでにご活躍中のコーディネーターの方の中には「ブログ、何を書けばいいの?」と悩んで手が止まってしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「Instagramは毎日投稿して『いいね』も付くけれど、なかなか高単価のコーディネート依頼に繋がらない」
「ブログを開設したはいいけれど、何を発信すればお客様の心に届くのか分からない」
そんなお悩みを抱えているかもしれません。
SNS(インスタ)は美しい写真で「出会い」を作るのには非常に強いツールです。
しかし、それだけではお客様が数十万円、数百万円のご依頼を決断する「最後の決め手」にはなりにくいのが現実です。
実際、フリーランスで20年活躍されているコーディネーターの方が、集客の6割をブログから得ているという事例もあります。
なぜなら、お客様は「この人は何ができるのか」「この人はどんな人なのか」を、ブログの記事を隅々まで読んで判断しているからです。
この記事では、SNSとは決定的に異なるブログの「戦略的役割」を解き明かし、お客様に「この人にお願いしたい」と心から思ってもらうために不可欠な「専門性(What)」と「人柄(Who)」を伝える、具体的な記事カテゴリー10選を徹底解説します。
目次
なぜ今、SNS(インスタ)だけでなく「ブログ」なのか?
まず、なぜ忙しい中でインスタに加えてブログまで運営する必要があるのか、その根本的な理由からご説明します。
SNSとブログは、情報の性質が全く異なります。
- SNS(インスタ、TikTokなど): 情報が次々と流れていく「フロー型」メディアです。投稿は一時的に注目されますが、すぐに過去の情報として埋もれてしまいます。
- ブログ: 良質な記事が蓄積されていく「ストック型」メディアです。「狭い部屋を広く見せるコツ」といった良質な記事は、1年後、3年後も検索エンジン経由で新しいお客様を呼び込み続ける「資産」となります。
お客様があなたに仕事を依頼するまでのプロセス(購買プロセス)において、両者が果たす役割は明確に違います。
SNSは「出会いの場」
美しいコーディネート写真やリール動画で、お客様に「知ってもらう」ための場所です。
「わあ、素敵だな」という憧れや共感を呼びます。
ブログは「信頼を築き、選ばれる場」
SNSで興味を持ったお客様は、次に「この人ってどんな人?」「本当に信頼できるプロなの?」と疑問に思い、プロフィール欄のURLをクリックします 2。
その飛び先であるブログが、あなたの「公式な顔」となるのです。
お客様はそこで、あなたの過去の実績、サービスの詳細、料金体系、そして「インテリアへの考え方」を隅々まで読みます。
高額なインテリアコーディネートは、「いいね」の数ではなく、「この人は私の悩みを深く理解し、解決してくれる専門家だ」という信頼によって初めて成約するのです。
インスタだけでご依頼が来ないと悩んでいる場合、その「出会い(SNS)」と「成約(ご依頼)」の間にある、「信頼構築(ブログ)」のステップが欠けているのかもしれません。
SNSとブログの役割比較(集客プロセスにおける違い)
| 比較項目 | SNS (例: Instagram) | ブログ (例: WordPress) |
| 情報の性質 | フロー型(一時的) | ストック型(永続的・資産) |
| 主な目的 | 認知拡大・「出会い」の創出 | 信頼構築・「選ばれる」決め手 |
| 情報探索性 | 低い(過去の投稿は埋もれる) | 高い(カテゴリ別・検索可能) |
| 伝える情報 | 雰囲気・世界観・速報性 | 専門知識・論理・人柄・サービス詳細 |
| 顧客心理 | 「素敵だな」(共感・憧れ) | 「この人だ」(信頼・安心) |
ブログで発信すべき「2つの軸」とは?
では、その「信頼」を構築するために、ブログで具体的に何を発信すればよいのでしょうか。
「2つの軸」とは
集客に成功しているブログには、必ず「2つの軸」が存在します。
それは、ベテランのコーディネーターが「この人は何ができるのか(What)」と「この人はどんな人なのか(Who)」を明確に伝えていることからも明らかです。
専門性 (Expertise):「何ができるか」を証明する
お客様の「私のこの悩み、解決できる?」という疑問に答える軸です。
あなたのスキル、専門知識、実績を具体的に示し、「プロとしての信頼」を獲得します。
これには、素材や製造方法に関する解説や、専門家としてのアドバイスが含まれます。
例えば、エコ素材の活用や持続可能なデザイン提案といった専門性も、顧客満足度向上に繋がる重要なアピールポイントです。
人柄 (Personality):「どんな人か」を伝える
お客様の「この人と気持ちよく仕事できる?」という不安に答える軸です。
あなたの価値観、仕事への情熱、インテリアへの想い、そしてあなた個人の魅力を示し、「人間としての安心感・共感」を獲得します。
失敗するブログと成功するブログの決定的な違い
この2軸のバランスがいかに重要か、具体的な例で見てみましょう。
失敗するブログの共通点
あるコーディネーターのAmebloブログを開いたとします。
しかし、記事一覧が「海外旅行」「国内旅行」ばかりだったら、どう感じるでしょうか 6。
これは「人柄(旅行好きな人)」(軸2) だけを発信している状態です。
読者(未来のお客様)は、「この人が何ができるか(専門性)」(軸1) を全く知ることができません。
結果として、ブログは単なる「日記」となり、ビジネス(集客)には繋がらないのです。
成功するブログの共通点
一方で、集客に成功しているコーディネーターのブログ 7 を見ると、記事一覧には「コーディネート事例(Works)」「手描きパース(スキル)」(軸1) と、「読書記録」「ロンドン見学ツアー(インスピレーション)」「人生でやりたい100のこと(価値観)」(軸2) が見事に混在しています。
これこそが「専門性」と「人柄」の黄金バランスです。
お客様は「この人は確かなスキル(パース)と実績(Works)がある」と信頼し、同時に「この人(本好き、ロンドン好き、こんな価値観の人)と趣味が合いそう」と共感します。
この「信頼」と「共感」が揃ったとき、お客様は安心して「この人にお願いしよう」と決断できるのです。
「専門性」を伝える記事ネタ5選
ここからは、お客様に「プロとしての信頼」を感じてもらうための具体的な記事ネタをご紹介します。
【ネタ1】コーディネート事例(Before/After)
あなたの「実績」を証明する最も強力なコンテンツです 7。
しかし、単に美しいAfterの写真を載せて「キレイになりました」と書くだけでは不十分です。「物語」として伝えましょう。
- 1. Before(お客様の課題): 「リビングが狭く、収納がない」「テレワークスペースが欲しい」など、具体的な悩み。
- 2. Process(提案プロセス): お客様の要望をどうヒアリングし(ヒアリング力は重要です)、どんな提案をしたか。なぜそのデザイン(例:エコ素材の活用)を選んだのか、その論理的な理由。
- 3. After(解決): 写真と共に、お客様の課題が「どう解決されたか」を具体的に解説。
- 4. お客様の声: 信頼性を高める第三者の評価。
【ネタ2】お悩み解決ノウハウ(How-to記事)
未来のお客様が「今、検索している悩み」に先回りして答える記事です。これはSEO(検索エンジン最適化)に最も効果的です。
ネタ探しに困ったら、AIに「家具の選び方のヒントを質問形式で展開して」と尋ねてみるのも良い方法です。
また、実際のお客様からよく聞かれる質問をリストアップするのも鉄板です。
(記事タイトルの具体例)
- 「失敗しないカーテン選び3つの法則:色・素材・機能の完全ガイド」
- 「狭い玄関を広く見せる照明と鏡の魔法の使い方」
- 「テレワークが劇的に快適になる書斎づくりとデスク選び」
【ネタ3】専門知識の解説(プロの視点)
「さすがプロ」と思わせる、専門家ならではの深い知識を発信します。
お客様が自分で調べても分からない、一歩踏み込んだ情報を提供しましょう。
(記事タイトルの具体例)
- 「無垢材と突板、どちらを選ぶべき?製造方法とメリット・デメリットを徹底比較」
- 「2025年最新トレンド:LIXILの新キッチン『〇〇』をプロが辛口レビュー」
- 「なぜ今、持続可能な素材(エコ素材)なのか?プロが注目する理由」
【ネタ4】サービス内容の「徹底解説」
お客様の「料金は?」「どこまでやってくれる?」という最大の不安を解消し、透明性を高めます。料金やプロセスが不明瞭なままでは、お客様は問い合わせをためらってしまいます。
(記事タイトルの具体例)
- 「初回ご相談からお引き渡しまでの全ステップを徹底解説」
- 「料金プランA(〇〇円)とB(〇〇円)の違いと、それぞれで実現できること(事例付き)」
- 「コーディネーターに依頼するメリットと、ご自身でやることの比較」
【ネタ5】こだわりのツール・スキル紹介
あなた独自の「強み」をアピールします。
他のコーディネーターにはない、あなただけの武器を記事にしましょう。
(記事タイトルの具体例)
- 「なぜ私が今も手描きパース(Copic)にこだわるのか」
- 「(元店舗デザイナーが教える)商業施設デザインの経験を住宅に活かす方法」
- 「リフォーム・リノベーションも得意です。構造から考えるインテリア提案」
「人柄」を伝える記事ネタ5選
次に、お客様に「人間としての安心感・共感」を抱いてもらい、「この人にお願いしたい」と思ってもらうための記事ネタです。
【ネタ6】自己紹介と「理念(想い)」
単なる経歴書(レジュメ)ではありません。あなたの「物語」と「情熱」を伝えます。
(記事に含める要素)
- 「私がインテリアの道に進んだ理由(例:子供の頃から家具配置が好きだった)」
- 「なぜ独立したのか? どんなお客様を幸せにしたいのか」
- 「私が提案したい〇〇な暮らし(例:身軽に暮らすお手伝い)というミッション」
【ネタ7】インスピレーション源
あなたの「センス」や「好み」の背景を見せることで、お客様は自分の好みと合うかどうかを判断できます。
(記事タイトルの具体例)
- 「プロが何度も読み返す、私のバイブル(神本)インテリア本5選」
- 「ロンドンのホテルデザインから学んだ、色使いのヒント」
- 「最近訪れた素敵なカフェ〇〇(国内街歩き)と、その内装デザイン」
【ネタ8】お客様の声・インタビュー
「専門性」の章で紹介した「事例」とは別に、「お客様との関係性」にフォーカスします。
あなたがお客様とどう向き合っているかを見せましょう。
(記事タイトルの具体例)
- 「お客様と二人三脚で乗り越えた、リノベーション秘話」
- 「(お客様へのインタビュー)依頼する前、一番不安だったことは何ですか?」
- 「『〇〇さんだったから、本音で話せました』と言っていただけた理由」
【ネタ9】仕事の裏側(Vlog風)
完成した美しい写真だけでなく、プロフェッショナルな「日常」を見せることで、仕事への真摯な姿勢が伝わります。
(記事タイトルの具体例)
- 「最新トレンドをキャッチ!インテリア展示会〇〇参加レポート」 7
- 「現場でのこだわり:私が『細部に執着する』理由」 7
- 「最高のチーム:いつも支えてくれる職人さんたちのご紹介」 5
【ネタ10】個人的なコラムや見解(エッセイ)
あなた個人の「価値観」を共有することで、強い共感を呼びます。
例えば、あるコーディネーターが「私はパーティが苦手な性格です」 と書いたとします。
これを見た「私も人混みより家でゆっくり過ごすのが好き」というお客様は、「この人なら私の(内向的な)気持ちを分かった上で、居心地の良い空間を提案してくれる」と、他のどのコーディネーターよりも強い共感を覚えるかもしれません。
スキルが同等なら、お客様は「自分と価値観が合う」と感じる人を選びます。あなたの「WISH LIST 100」や「嫌いなこと20」といった一見仕事と関係ないような個人的な好みこそが、最強のブランディングになり得るのです。
「書く場所」はどこが最適?目的別ブログプラットフォーム比較
「何を書くか」が決まったら、次に「どこで書くか」という問題があります。
Ameblo、note、WordPress…どれを選ぶべきでしょうか。
結論から申し上げます。
本気で集客し、ブログをあなたの「資産」にしたいなら、WordPress(ワードプレス)一択です。
なぜなら、Amebloやnoteは「他社のプラットフォーム」だからです。
どれだけ良い記事を書いても、それは「間借り」している状態に過ぎません。
- リスク: 規約違反と判断されたり、運営会社の都合で、ある日突然アカウントが削除されたり、サービスが終了するリスクが常につきまといます。あなたの「資産」が他人の都合で消える可能性があるのです。
- ブランディング: インテリアコーディネーターという「美しさ」や「世界観」を売る職業において、全員と同じデザインのnoteを使うことは、あなたの専門的なブランドイメージを十分に伝えきれない可能性があります。
- SEO: WordPressはSEOに非常に強く、高度な設定が可能です。あなたの記事(資産)を検索上位に表示させ、長期的に集客し続ける「エンジン」を構築できます。初期アクセスはゼロですが、数ヶ月後にはSNSを遥かに超える集客効果を生む可能性があります。
WordPress vs note 徹底比較(集客・ブランディングの観点)
| 比較項目 | WordPress (推奨) | note (参考) |
| 運営コスト | 有料(月1,000円程度〜) | 無料 |
| 所有権 | あなた(完全な資産) | note社(削除リスクあり) |
| デザイン | ほぼ無限(ブランド構築に最適) | 制限あり(差別化困難) |
| SEO対策 | 非常に強い(高度な設定可) | 弱い(基本設定不可) |
| 集客の速さ | 遅い(最初はアクセスゼロ) | 早い(初期アクセスあり) |
| 商用利用 | 自由(アフィリエイト等も可) | 制限あり(Amazon以外ほぼ不可) |
手軽さでnoteを選ぶこともできますが、ビジネスとして長期的な資産を築くなら、最初からWordPressで「自分のお店(=独自ドメインのサイト)」を構えることを強くお勧めします。
読者を「ご依頼」につなげる最後のステップ
良質な記事を書いても、読者が「読んでよかった」で終わってしまっては、集客には繋がりません。
記事を読み終えた読者が「次に何をすればいいか」迷わないよう、必ず「次の行動」への導線(CTA=Call to Action:行動喚起)を用意しましょう。
CTAは、すべての記事の末尾に設置するのが基本です。
記事タイプ別のCTA具体例
記事の内容によって、お客様の心理状態に合わせたCTAを設計するのがコツです。
「専門性」の記事(事例、ノウハウ)を読んだ後
(悩みや課題が明確になり、プロの技に感心している状態)
- 「〇〇様と同じお悩みはありませんか? まずは無料相談でお聞かせください」
- 「サービス・料金一覧はこちら」
- 「他のコーディネート事例(ポートフォリオ)はこちら」
「人柄」の記事(理念、コラム)を読んだ後
(あなたへの共感や好感が高まっている状態)
- 「私の想いに共感いただけたら、ぜひサービス紹介ページもご覧ください」
- 「私のこだわりが詰まったコーディネート事例集もご覧になりますか?」
- 「最新情報やブログの更新をニュースレターでお届けします(準備中でもOK)」
ポイント: CTAは「今すぐご契約を」のような高圧的なものではなく、「心理的な負担が少ない」ものに設定し、お客様が安心して次のステップに進めるように配慮しましょう。
まとめ

インテリアコーディネーターのブログは、単なる日記帳ではありません。
あなたという専門家の「信頼」をストックしていく、未来のお客様との「出会いを育てる資産」です。
SNS(インスタ)で「出会い」、ブログで「深く知り、信頼してもらう」。
この連携を意識することが、Web集客成功の鍵となります。
何を書くか迷ったら、この記事でご紹介した「専門性(What)」と「人柄(Who)」の2つの軸を思い出してください。
この両輪をバランスよく発信し続けることが、ご依頼が途切れないコーディネーターへの一番の近道です。
まずは1記事、書いてみませんか。
「あなたの最高のビフォーアフター事例」か「あなたが、なぜこの仕事をしているのかという情熱」。
どちらでも構いません。
未来のお客様に届けるつもりで、あなたの想いを記事にしてみてください。
お問い合わせはこちら
当社ではホームページの制作と管理をおこなっています。
ホームページの管理費は月額換算で3,300円です(年払い税込39,600円)。
ホームページの管理をさせて頂いているお客様には、ブログ記事の書き方に関するご相談なども受けております。
これから作るホームページの制作、現在お持ちのホームページのリニューアルや保守管理に関してなど、ホームページに関することはなんでもお気軽にご相談ください。