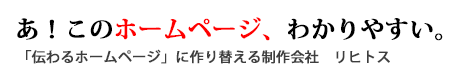「放課後等デイサービスのブログ、何を書けばいいか分からず、更新が止まっている」
「日々の支援に追われて、なかなか広報まで手が回らない…」
「がんばって書いているのに、まったく反応がない…」
このようなお悩みをお持ちの施設運営者様、現場スタッフの皆様は非常に多いのではないでしょうか。
近年、放課後等デイサービス(放デイ)の施設数は急速に増加しており、競争は激化しています。
保護者の皆様は、数多くの選択肢の中から、大切なお子様を預ける施設を真剣に探しています。
どんなに素晴らしい療育を実践していても、その魅力が伝わらなければ「選ばれる施設」になることは難しい時代です 。
この記事では、「ブログで何を書くか」という具体的なネタはもちろん、その記事が「なぜ」必要なのか、そして「どう書けば」保護者様や関係機関、未来のスタッフの心に届くのかをわかりやすくご説明したいと思います。
目次
放課後等デイサービスがブログを運営する3つの大切な「目的」

ブログのネタ探しを始める前に、まずはブログを書く「目的」をご説明したいと思います。
放デイのブログの目的は、単なる「集客」だけではありません。
むしろ、ブログの価値は、施設の中で行われている目に見えない「支援の質」や「あたたかい雰囲気」を、目に見える形(=記事)にして届ける「見える化」にあります。
この「見える化」は、主に3つの大切な相手に届けるために行います。
【目的1】保護者との信頼関係を築く
放デイをお探しの保護者様が、心の中で抱いている最大の不安は「この施設に、うちの子を任せて本当に大丈夫だろうか?」という一点に尽きます。
特に、大切なお子様が施設でどのように過ごしているかは、最も知りたい情報です。
ブログを通じて、日々の活動の様子、楽しそうなお子様の(許可を得た)写真、そして支援するスタッフの優しい表情や人柄を公開すること。
これが、施設の「透明性」を高めて、保護者様にとっての「安心材料」となります。
【目的2】関係機関との信頼関係を築く
ブログは、保護者様だけでなく、学校の先生や相談支援専門員といった「関係機関」への重要な報告ツールにもなります。
「日々の療育プログラムの内容や、お子様がどのような活動(プログラム活動)でどんな表情を見せているかを具体的に発信すること」、それは、施設が「個別支援計画書」に基づいて、専門的な療育をしっかりと実践していることの証明となります。
関係機関からの「この施設は、専門性を持ってしっかり支援しているな」という専門的な信頼は、日々のスムーズな連携に不可欠です。
【目的3】求職者に「働きがい」と「理念」を伝える
ブログは、そのまま「採用ツール」としても機能します。
求職者(児童指導員や保育士など)は、応募前や面接後に、その施設のホームページやブログをチェックし、「どんな雰囲気の職場だろうか」「どんな理念を持って支援しているんだろうか」を確認します。
ブログでスタッフの笑顔や支援へのこだわり、施設の理念を発信することで、その価値観に共感する人材が集まりやすくなり、採用後のミスマッチを防ぎ、質の高い人材確保に繋がります。
これら3つの目的(保護者・関係機関・求職者)は、バラバラのものではありません。
例えば、「専門的な療育プログラムの紹介記事」という1つの記事は、保護者様には「質の高い支援への安心」を、関係機関には「計画的な支援を行う専門性」を、求職者には「スキルアップできる働きがい」を、同時に伝えることができるのです。
この多角的な視点を持つだけで、ブログ記事の「価値」は格段に上がります。
放課後等デイサービスのブログ記事カテゴリー7選
目的が明確になったところで、いよいよ「何を書くか」です。
ここでは、前章の「3つの目的」をすべて達成するための、具体的かつ実践的な記事ネタを7つのカテゴリーに分類してご紹介します。
記事ネタ カテゴリー別 目的マトリクス
まずは、どのネタが、誰に、どんな効果をもたらすのかを一覧で見てみましょう。
| カテゴリー | 主な対象と目的(◎:非常に関連, 〇:関連) | 具体的な記事内容の例 |
| 1. 日々の活動報告 | ◎保護者様(安心感), 〇関係機関(様子伺い) | 今日のSST、クッキング療育、公園での運動の様子、制作活動の作品紹介 |
| 2. 専門的な療育解説 | ◎関係機関(専門性), 〇保護者様(信頼感) | 5領域に基づく支援、SSTの目的、ビジョントレーニング、認知行動の解説 |
| 3. スタッフ紹介 | ◎保護者様(安心感), ◎求職者(魅力づけ) | 児童指導員、保育士、理学療法士などの専門資格、経歴、支援への想い、趣味 |
| 4. 保護者の声 | ◎保護者様(信頼感・共感) | 利用のきっかけ、お子様の変化、施設への感想 |
| 5. 施設の理念と強み | ◎全対象(差別化) | なぜこの施設を立ち上げたのか、他施設との違い(例:運動特化、学習支援特化など) |
| 6. イベント告知・報告 | 〇保護者様(期待感), 〇地域の目(交流) | 夏祭り、クリスマス会、遠足、地域交流イベントの様子 |
| 7. お知らせ・Q&A | ◎保護者様(利便性) | 空き状況、送迎ルートの変更、感染症対策、保護者様からよくある質問への回答 |
各カテゴリーの「書き方」のコツ
1. 日々の活動報告
最も基本的で、最も保護者様の安心感を与える記事です。
但し、単に「みんなで積み木をして楽しそうでした」といった内容だけでは不十分です。
「この積み木遊びには、手先の巧緻性(微細運動)や空間認知能力を高めるという支援の意図があります」のように、療育の目的を一言添えるだけで、専門性が格段に伝わります。
2. 専門的な療育解説
厚生労働省のガイドラインに基づく「5領域」や、施設独自の「療育プログラム」を、保護者様にも分かりやすい言葉で解説する記事です。
これは関係機関へのアピールにも最強のコンテンツとなります(詳しくは後述します)。
3. スタッフ紹介
支援は「人」です。療育の質はスタッフの質で決まります。
どんな専門性を持ったスタッフが、どんな想いで支援にあたっているのか、その「顔」や「人柄」が見えることは、保護者様の安心に直結します。
4. 保護者の声
「利用前は不安だったが、通い始めてからこんな変化があった」という具体的なエピソードは、施設側が100回「素晴らしい支援です」と言うよりも説得力があります。
5. 施設の理念と強み
競争が激化する今、「なぜ、あなたの施設でなければならないのか」を言語化することが重要です。
施設長の支援への熱い想いや、他にはない独自の強み(例:専門職の配置、送迎体制など)を明記しましょう。
6. イベント告知・報告
季節ごとのイベントは、ブログの「華」となる記事です。
施設の明るく楽しそうな雰囲気を伝える絶好の機会です。
7. お知らせ・Q&A
「空き状況」や「送迎範囲」など、保護者様が具体的に知りたい実務的な情報も、ブログで定期的に発信すると親切です。
読まれる記事の「書き方」と「見せ方」

素晴らしいネタ(中身)があっても、それが読みにくかったり、伝わりにくかったりしては意味がありません。
多忙な保護者様にも「スッと頭に入り」「心に届く」文章術をご紹介します。
結論から伝える「PREP(プレップ)法」
PREP法とは、「Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(結論)」の順で文章を構成する技術です。
ビジネス文書でよく使われますが、「結論が分かりやすくなる」「説得力が生まれる」というメリットがあり、これは放デイの活動報告ブログに最適です。
【放デイブログでのPREP法 活用例】
- P(結論): 本日のSST(ソーシャルスキルトレーニング)では、「順番を待つ」練習をしました。
- R(理由): なぜなら、集団生活の中で、お友達と楽しく遊ぶためには「待つ」というスキルがとても大切だからです。
- E(具体例): 最初はそわそわしていたA君も、タイマー(視覚支援)を見て「あと少しだ」と自分に言い聞かせることができました。Bさんはお友達に「次、貸してね」と自分から声をかけることができました。
- P(結論): 最後はみんなで仲良く順番を守って遊ぶことができ、お子様たちも「できた!」と誇らしげな顔を見せてくれました。
放デイのブログは、エッセイである必要はありません。
多忙な保護者様が「今日は何をしたか」「どんな成長があったか」を短時間で正確に把握できることが重要です。
PREP法が長文には向かないと言われる場合もありますが、それは逆に、簡潔な報告が求められる放デイのブログには最適であると言えます。
読者の「検索ニーズ」から逆算する記事の設計図
読まれる記事は「設計図(構成案)」が9割です。
いきなり書き始めるのではなく、まず「誰が、何に悩んで、この記事にたどり着くか」をイメージします。
例えば、「放課後等デイサービス 〇〇市」で検索する保護者様は、どんな情報を求めているでしょうか?
書き出しに「〇〇市で放デイをお探しですか? お子様のこんな特性(例:お友達との関わり、言葉の遅れなど)でお悩みではありませんか?」と問いかけることで、読者を「この記事は私のための記事だ」と惹きつけることができます。
ブログを見つけてもらう技術(SEO・MEO)
素晴らしい記事も、読まれなければ存在しないのと同じです。
ここでは、あなたの施設を「見つけてもらう」ための技術を、専門的な視点から分かりやすく解説します。
SEOの基本と「E-E-A-T」という”信頼”の物差し
SEO(Search Engine Optimization)とは、Googleなどの検索結果で、自施設のブログを上位に表示させるための対策です。
特に、放デイのような医療や福祉、金融など、人々の生活に大きな影響を与えるジャンル(YMYL: Your Money Your Lifeと呼ばれます)では、Googleは「E-E-A-T」という基準を非常に重視します 15。
- E (Experience): 経験(実際に支援を行った経験)
- E (Expertise): 専門性(資格を持った専門職による療育)
- A (Authoritativeness): 権威性(地域の相談支援事業所や行政からの信頼)
- T (Trust): 信頼性(運営法人の情報が明確に開示されていること)
このE-E-A-T、何だか難しそうに聞こえますが、心配ありません。
実は、先述しました「書くべきネタ」を誠実に発信することこそが、最強のE-E-A-T対策(=SEO対策)なのです。
- 「日々の活動報告」は、あなたの施設の「経験」を証明します。
- 「専門的な療育解説」や「スタッフ紹介」は、「専門性」を証明します。
- 「保護者の声」や「関係機関との連携」は、「権威性」と「信頼性」を証明します。
- 「運営法人情報の開示(16)」は、「信頼性」の根幹です。
小手先のSEOテクニック よりも、日々の支援の様子を「透明に」発信し続けること。
それこそが、Googleの評価(SEO)と保護者様の評価(信頼)を同時に高める、唯一にして最強の道です。
「MEO(Googleビジネスプロフィール)」の活用
SEOと並んで、今や放デイの集客に欠かせないのが「MEO」です。
MEOとは、「〇〇市 放課後デイ」と検索した時に、Googleマップ(地図)と一緒に出てくる施設情報を最適化することです。
これは「Googleビジネスプロフィール」という無料のツールで管理できます。まずはご自身の施設を登録し、オーナー確認を済ませてください。
MEOとブログは、それぞれ「集客の入り口」と「信頼の受け皿」という重要な関係性にあります。
【保護者様が施設を見つけるまでの流れ】
- 保護者様が「〇〇市 放デイ」と検索します。
- MEO(Googleマップ)が検索結果の上位に表示されます。
- 保護者様は、地図上で場所を確認し、口コミや写真を見て興味を持ちます。
- MEOに登録されている「ウェブサイト(ブログ)」のリンクをクリックします。
- ブログに飛び、日々の活動報告 や保護者の声 を読み、支援の質と雰囲気を深く理解し、信頼します。
- 「ここなら安心できそう」と、電話やメールで問い合わせをします。
MEO対策で「見つけてもらい」、ブログ(ホームページ)で「信頼してもらう」。この連携こそが、現代の放デイ集客の王道です。
知らないと危険! ブログ運営の「コンプライアンス(法令遵守)」
信頼を得るために始めたブログが、たった一つのミスで、施設の信頼を失墜させる原因になっては絶対になりません。
放デイは、児童福祉法 に基づく公的な福祉サービスです。
専門家として、必ず守るべき3つのルールを、厳しめにお伝えします。
【お子様の写真掲載】「同意書」は必須、掲載時の「一文」も忘れずに
お子様の笑顔は、ブログで最も魅力的なコンテンツです。
しかし、その取り扱いには細心の注意が必要です。
お子様の顔写真をホームページやブログに掲載するには、「保護者の許可」を取るようにしましょう。
同意なしの掲載は、お子様のプライバシー権や肖像権の侵害にあたる可能性があります。
ブログ記事の末尾に「※掲載している写真はお子様・保護者様の同意を得たもののみです」という一文があると、見ている側も安心します。
これは、記事を見た他の保護者様(特に、写真掲載を許可していない保護者様)に対して、「この施設はプライバシーにしっかり配慮している」という安心感を与える、非常に重要な一文となります。
【誇大広告】「日本一」「必ず治る」はNG(景表法・医療広告ガイドライン)
放デイ(福祉サービス)も、医療機関と同様に「誇大広告」は厳しく規制されます。
景品表示法や医療法の観点から、以下のような客観的根拠のない表現は「不当表示」や「誇大広告」とみなされるリスクが極めて高いです。
- NG表現の例:
- 「地域No.1の支援実績!」
- 「このプログラムで必ず改善します!」
- 「日本最高の療育を提供します!」
なぜなら、これらの表現は、利用者に「誤認」を与え、適切な施設選びを妨げる可能性があるためです。
常に行った支援の「事実」のみを記述する姿勢が求められます。
支援プログラムの「公表義務」
さて、ここまで「何を書くべきか」を解説してきましたが、最後に「書かなければならないこと」についてお伝えします。
すでにご存知の通り、2024年(令和6年度)の障害福祉サービス報酬改定により、児童発達支援と放課後等デイサービスにおいて、「支援プログラムの公表」が義務となりました。(参考:こども家庭庁『児童発達支援等における 支援プログラムの作成及び公表の手引き』)
そして、この支援プログラムを(原則としてインターネットで)公表していない場合、「支援プログラム未公表減算」として、所定の単位数が減算(=ペナルティ)されることになりました。
多くの運営者様は、「減算を避けるために、仕方なくプログラムを公表しなきゃ」と、この義務を「面倒なタスク」として捉えているかもしれません。
しかし、この「公表が義務化された支援プログラム」こそが、あなたのブログで書くべき「最強のネタ」なのです。
この「面倒なタスク」を、最高の「機会」に変える具体的な行動プランを提案します。
- まず、作成が義務付けられている「支援プログラム」を用意します。(5領域:①健康・生活、②運動・感覚、③認知・行動、④言語・コミュニケーション、⑤人間関係・社会性)。
- この、やや堅苦しい「お役所向けの文書」を、そのままホームページにPDFファイルとして掲載して「はい、義務完了」では、あまりにもったいないです。
- そのプログラムの内容を【5つの領域】に分割します。
- そして、第2章で紹介した「専門的な療育解説」の記事として、保護者様にも分かりやすい言葉(先述したPREP法などを活用)で、日々の活動写真を交えながら、ブログ記事としてリライト(再編集)して連載するのです。
このやり方の4つのメリットを整理します。
- 【コンプライアンス達成】: 支援プログラム未公表減算を回避できます。
- 【ブログネタの確保】: 最低でも5回分(5領域)の、非常に質の高いブログネタが確保できます。
- 【SEO(E-E-A-T)達成】: 「専門性(Expertise)」と「信頼性(Trust)」の証明となり、Googleからの評価(SEO)が高まります。
- 【保護者様の信頼獲得】: 「この施設は、こんなにしっかりした根拠を持って、計画的に支援してくれているんだ」という信頼を得ることができます。
義務化されたタスクを、施設の「信頼」と「集客」につなげるチャンスに変えましょう。
まとめ

「放課後等デイサービスで、ブログに何を書くか」という悩みは、そのまま「私たちは、どのような支援を、どのような想いで社会に届けたいか」という、皆様自身の「理念」への問いに繋がっています。
ブログは、施設様の「支援の質」や「お子様への真摯な想い」を社会に伝えるための、最も誠実で、最も強力なツールです。
競争が激化する今、SEOやMEOといった技術的な対策も重要です。
しかし、保護者様との信頼関係を築く根幹にあるのは、日々の支援を「透明に」見せるという、誠実な姿勢に他なりません。
完璧な記事を目指す必要はありません。
まずは今週のお子様の「できた!」という笑顔の瞬間を、「支援の意図(なぜ、その活動を?)」と「安全への配慮(写真の同意 )」を一言添えて、発信することから始めてみてください。
皆様の素晴らしい支援が、それを必要としている未来の保護者様と、お子様へ届くことを心から願っています。
お問い合わせはこちら
当社ではホームページの制作と管理をおこなっています。
ホームページの管理費は月額換算で3,300円です(年払い税込39,600円)。
ホームページの管理をさせて頂いているお客様には、ブログ記事の書き方に関するご相談なども受けております。
これから作るホームページの制作、現在お持ちのホームページのリニューアルや保守管理に関してなど、ホームページに関することはなんでもお気軽にご相談ください。