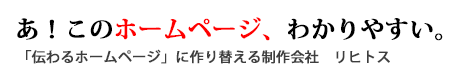目次
工務店のブログは何を書けばいいの?

「ブログ、何を書けばいいか分からない…」
「毎日現場の様子を更新しているのに、一向に問い合わせが来ない」
「とうとうネタが尽きてしまった…」
工務店のブログを運営されている皆様が、一度は抱える共通の悩みではないでしょうか。
しかし、ブログの重要性は増すばかりです。
現代の家づくり検討者の動向として、総務省の統計などでも示されている通り、住宅の購入やリフォームを検討する人の多くの人が、まず最初にインターネットで情報収集を始めます。
ブログは、広告費をかけずに、未来のお客様と出会い続けることができる、工務店にとって最強の「資産」です。
一方で、よくある失敗例として、「今日の現場」という日記や、専門的すぎる技術用語の羅列、写真だけを並べた施工事例が挙げられます。
これでは、お客様が検索する「悩みの答え」になっておらず、残念ながら想いは届きません。
この記事では、単なるネタ一覧をご紹介するのではありません。
「誰に」「何を」伝えるかという戦略から、SEO(検索エンジン最適化)で評価され、実際にお問い合わせに繋げるための「記事の書き方」まで、専門家が徹底的に解説します。
この記事を読めば、もう「何を書くか」で迷うことはありません。
集客できる工務店ブログの「絶対原則」
記事のネタを探す前に、まずは集客できるブログの「土台」となる原則を3つご紹介します。
【原則1】工務店SEOの核は「ローカルSEO」
まず大前提として、大手ハウスメーカーと全国区で戦う必要は一切ありません。地域密着型の工務店様にとっての主戦場は、ご自身の「商圏(地域)」です。
SEOの基本戦略は「地名 × 〇〇」です。
- (例)「世田谷区 注文住宅」「〇〇市 リフォーム 費用」「〇〇町 工務店 評判」
中小の工務店様こそ、このローカルSEOが効果を発揮しやすいのです。
なぜなら、大手には書けない「〇〇市のこの地域は地盤が弱い」「〇〇小学校区の土地事情」といった、その地域特有の悩みに寄り添った、具体的で親身な記事が書けるからです。
【原則2】「誰に」「何を」伝えるかを明確にする

あなたのブログは、「誰」の「どんな悩み」を解決するためのものでしょうか?
ターゲット(ペルソナ)を具体的に設定することが、心に響く記事の第一歩です。
- (ペルソナ例)
- 〇〇市在住、30代夫婦、子供1人。
- 土地探しから始めている。
- 耐震性と断熱性(省エネ)にはこだわりたい。
- 総予算は〇〇円くらいで、費用内訳が不安。
このペルソナが検索しそうなキーワード(例:「〇〇市 土地探し コツ」「耐震等級3 必要か」「注文住宅 諸費用 とは」)こそが、あなたが書くべき記事のテーマになります。
【原則3】ブログは「信頼」を積み上げる場所

家は、お客様にとって人生で最も高額な買い物の一つです。
だからこそ、お客様は「この会社は信頼できるか?」を厳しく見ています。
ブログを通じて、貴社の技術力、豊富な実績、そして何より「スタッフの人柄」や「家づくりへの想い」 を継続的に発信することが、最終的な「決め手」としての信頼に繋がります。
キーワードの「温度感」でお客様の心理を読み解く
ここが最も重要な戦略です。
検索キーワードには、お客様の「温度感(本気度)」が明確に表れています。
この温度感に合わせて記事を書き分けることが、SEO戦略の核となります。
お客様の心理は、大きく以下の3つの段階に分かれます。
- 低温度(潜在層): まだ家づくりは具体的でないが、暮らしやお金に関連する情報を収集している層。
- 中温度(顕在層): 家づくりを検討し始め、他社と比較したり、具体的な知識(費用、性能)を集めている層。
- 高温度(明確層): 依頼する会社を具体的に探しており、「地名×サービス名」などで検索する層。
多くの工務店様が、「高温度」のキーワード(例:「〇〇市 注文住宅」)ばかりを狙おうとします。
しかし、この層は競合が強く、獲得が困難です。
ブログの真の役割は、「低温度」「中温度」の層に役立つ記事(ブログ・解説記事)を提供し、信頼関係を築きながらファンになってもらう(育てる)ことにあります。
この戦略を視覚化すると、以下のようになります。
【表1】キーワードの「温度感」と戦略的記事マッピング
| 温度感(検索意図) | ユーザーの心理 | キーワード例 | 担当する記事タイプ | 記事のゴール |
| 高温度 (今すぐ客) | 「〇〇市でリフォームしたい」 「A工務店の評判は?」 | 「〇〇市 工務店 おすすめ」 「〇〇市 リフォーム 費用」 「[自社名] 評判」 | サービスページ 施工事例ページ お問い合わせページ | 今すぐの問い合わせ (CVRの最大化) |
| 中温度 (比較・検討客) | 「A社とB社の違いは?」 「耐震等級3って必要?」 「この間取りでいくらかかる?」 | 「工務店 ハウスメーカー 違い」 「耐震等級3 デメリット」 「注文住宅 費用 内訳」 | 施工事例(詳細版) 専門知識の解説記事 お客様の声 | 不安の解消 信頼の獲得 (比較検討の優位に立つ) |
| 低温度 (情報収集中) | 「家っていつ建てるのが得?」 「高気密高断熱って何?」 「土地探しってどうやるの?」 | 「住宅ローン 2025年」 「高気密高断熱 メリット」 「土地探し コツ」 | ブログ記事(ノハウ) 地域の情報記事 コラム | 役立つ情報提供 「専門家」としての認知 (メルマガ登録など) |
これを書けば間違いない!集客に繋がる「鉄板記事カテゴリ」7選
前章の「温度感」戦略に基づき、具体的に書くべき7つのカテゴリを、書き方のポイントと共に徹底解説します。
【カテゴリ1】施工事例:「会社の顔」となる最強のコンテンツ
施工事例は、工務店の実績をアピールする最大の武器であり、SEO対策としても極めて有効です。
- NGな書き方: 写真を数枚並べて「素敵な家ができました」だけ。これでは検索に引っかからず、お客様の「知りたいこと」に答えていません。
- OKな書き方: 1つの事例を「1記事」として、以下の要素を盛り込み、丁寧に書き上げます。
- タイトル: 必ず「地名」と「お客様の悩み・要望」を入れます。
- (例)「〇〇市|狭小地でも光溢れる。家族3人が快適に暮らす3階建て住宅の施工事例」
- Before/Afterの写真: 視覚的な変化を明確に(特にリフォーム)。
- お客様の悩み(Before): 「なぜ」この工事をしようと思ったのか?(例:「収納が少ない」「冬が寒かった」)
- 解決策の提案(Process): その悩みを「どう」解決したのか、プロの視点を交えて解説します。(例:デッドスペースに造作棚を、窓を複層ガラスに変更し断熱性を向上)
- 詳細情報(Data): お客様が最も知りたい具体的な情報です。
- 費用(「〇〇万円台」でも可)
- 工期(例:約〇ヶ月)
- 使用した素材(例:無垢材、断熱材の種類、キッチンメーカー名など)
- 建物の基本情報(坪数、間取り、工法)
- お客様の声: (カテゴリ2で後述)住み心地などを具体的に。
- タイトル: 必ず「地名」と「お客様の悩み・要望」を入れます。
過去の支援事例でも、施工事例に「費用・素材・工期」を明記しただけで、問い合わせが格段に増えたケースがあります。
お客様はリアルな情報を求めています。
【カテゴリ2】お客様の声・インタビュー:未来のお客様の「不安」を解消する
「お客様の声」は、未来のお客様が「自分たちに合った会社か」「不安をどう解消してくれたか」を知るための重要なコンテンツです。
- 書き方のポイント:
- 「ありがとうございました!」という感謝の言葉だけでは、情報は伝わりません。
- 以下の質問を軸にインタビューし、お客様の「生の声」を引き出しましょう。
- 家づくりを始める前、どんな「悩み」や「不安」がありましたか?
- なぜ他のハウスメーカーや工務店ではなく、当社を選んでいただけたのですか?(決め手)
- 計画中、一番こだわった点と、一番悩んだ点は何ですか?
- 実際に住んでみて、「住み心地」はいかがですか?(例:光熱費の変化、冬の暖かさ、お手入れのしやすさなど)
【カテゴリ3】専門知識・ノウハウ:「先生」として信頼を得る記事
お客様の「〇〇って何?」という疑問に、専門家として分かりやすく答える記事です。
これが「低温度」の検索ユーザー(未来の見込み客)をブログに集め、貴社を「専門家(先生)」として認知させます。
ポイントは、専門用語を並べるのではなく、読者の「メリット」「デメリット」「生活への影響」に変換して解説することです。
ここでは、特に反響の大きい3つの「深掘りネタ」をご紹介します。
【深掘りネタ例1:安全性】「耐震等級」を日本一わかりやすく解説します
日本は地震大国であり、お客様の安全性への関心は非常に高いです。
- 解説のポイント:
- 耐震等級1, 2, 3の違いを説明します。
- 等級1: 建築基準法で定められた「最低限」の基準(震度6強~7で倒壊しないレベル)。
- 等級2: 等級1の「1.25倍」の強さ。学校や病院などの避難所と同レベル 6。「長期優良住宅」の認定条件の一つです。
- 等級3: 等級1の「1.5倍」の強さ。消防署・警察署など防災の拠点となる建物と同レベルの、最高等級です。
- 背景: 1995年の阪神・淡路大震災の教訓から、より高い性能が求められるようになった背景も伝えましょう。
- 両論併記: メリット(安全性)だけでなく、デメリット(等級を上げるための建築コストが上がる可能性)も誠実に伝えることで、信頼性が高まります。
- 実利: お客様の「実利」に繋がる情報として、地震保険の割引率を必ず提示します。
- 耐震等級1, 2, 3の違いを説明します。
- 【表2】耐震等級 早わかり比較表
- 複雑な等級の違いと、金銭的メリット(保険料)を一覧化することで、お客様の「結局どれを選べばいいの?」という疑問に即座に答えます。
| 耐震等級 | 地震への強さ(目安) | 建築物の例 | 地震保険の割引率 |
| 耐震等級3 | 建築基準法(等級1)の1.5倍 | 消防署・警察署など | 50%割引 |
| 耐震等級2 | 建築基準法(等級1)の1.25倍 | 学校・病院(避難所) | 30%割引 |
| 耐震等級1 | 建築基準法で定める最低基準 | 一般的な住宅 | 10%割引 |
【深掘りネタ例2:市場トレンド・お金】「2025年の省エネ基準義務化」で何が変わる? 2024年に家を建てる人が損しないための全知識
法改正などは「書くべき」緊急性の高いトピックです。
- 解説のポイント:
- まず「高気密高断熱」の基本(UA値、C値など)を解説し、なぜ省エネが必要か(光熱費削減、ヒートショック防止、建物の耐久性向上)を説明します。
- 2025年4月から、新築住宅は「省エネ基準適合」が義務化されることを説明します。
- 【最重要】 ここからが本題です。義務化は2025年からですが、「2024年1月以降に建築確認を受ける住宅」は、「省エネ基準適合」でないと住宅ローン減税(0.7%・13年間)の対象外になってしまったことを、強く伝える必要があります。
- これは、お客様が数百万円単位で損をする可能性がある、非常に重要な情報です。この情報をいち早く発信することが、工務店への信頼に直結します。
- 【表3】2024年・2025年 住宅ローン減税(省エネ基準の影響)
- 「2024年からの制限」は、お客様の家計に直結します。この「今すぐ行動すべき理由」を視覚的に訴え、工務店の専門性と顧客本位の姿勢を示します。
| 住宅の省エネ性能 | 2023年末までに入居 | 2024年・2025年に入居(借入限度額) |
| 認定住宅(長期優良住宅など) | 5,000万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
| その他の住宅(省エネ基準非適合) | 3,000万円 | 0円(住宅ローン減税の対象外!) |
| ※2024年1月以降に建築確認を受けた場合 |
【深掘りネタ例3:お金の不安】「注文住宅の費用」を丸裸に!見積書の読み方と「諸費用」の罠
お客様が家づくりで一番不安なのは「お金」です。
総額が分かりにくいことが、不安を増長させます。
- 解説のポイント:
- 注文住宅の費用は、大きく「①本体建築工事費」「②付帯工事費(別途工事費)」「③諸費用」の3つに分かれていることを説明します。
- 「坪単価」だけを見てはいけない理由(②と③が含まれていないことが多い)を解説します。
- 特に分かりにくい「諸費用」の内訳(ローン手数料、登記費用、火災保険料、印紙代、地盤調査費など)を具体的にリストアップし、総額のどれくらい(例:5〜10%)を見ておくべきか目安を提示します。
- 見積書のサンプルを見せながら、「どこをチェックすべきか」を優しく解説します。
- お金の話をオープンにすることは、工務店の「透明性」と「誠実さ」を示す絶好の機会です。
【カテゴリ4】地域の土地・不動産情報:ローカルSEOの核
「エリアキーワード×悩みキーワード」を実践する、ローカルSEOの核となるカテゴリです。
「〇〇市で家を建てたい」人が必ず検索する情報を提供し、地元の専門家としての地位を確立します。
- ネタ例:
- 「〇〇市で土地探し。人気エリア(〇〇小学校区)の相場と注意点」
- 「〇〇市の地盤ハザードマップ解説と、工務店が行う地盤改良の方法」
- 「〇〇市で受けられるリフォーム補助金・助成金まとめ【2025年最新版】」
- (応用)リフォーム市場は巨大(6.2兆円規模)で、住宅ストックの多くがリフォーム適齢期です 17。また「空き家問題」もビジネスチャンスになります。「〇〇市 空き家 リノベーション 費用と実例」といった新築以外の切り口も非常に有効です。
【カテゴリ5】スタッフ・会社の紹介:顔が見える安心感
最終的に、人は「人」で選びます。高額な商品を扱う工務店こそ、「誰が」作っているのかを見せることが、他社との大きな差別化要因になります。
- ネタ例:
- 「社長が語る『なぜ私はこの地域で家づくりを続けるのか』」
- 「現場の番人!大工の〇〇さん(歴30年)の仕事道具とこだわり紹介」
- 「お客様と直接話す、設計士〇〇の1日のルーティンと家づくりへの想い」
- 「普段は見られない現場の作業風景:『基礎工事』ってここまでやるんです」
【カテゴリ6】よくある質問(FAQ):潜在的な疑問を先回りして解決
問い合わせるほどではないが、多くのお客様が抱く共通の疑問に、記事として先回りして答えます。
- ネタ例:
- 「工務店とハウスメーカー、結局どっちがいいの?メリット・デメリットを徹底比較」
- 「『相談無料』とあるけど、相談料や設計料は本当に不要ですか?」
- 「見学会に行くと、しつこい営業をされませんか?(当社の営業方針)」
- 「アフターメンテナンスはどこまで(何年)やってくれますか?」
【カテゴリ7】イベント情報:実際に行動を促す記事
ブログで信頼を築いたお客様の「受け皿」となる、行動(コンバージョン)のための記事です。
- ネタ例:
- 「〇〇市で完成見学会を開催!『高気密高断熱』を肌で体感できる2日間」
- 「【毎月3組限定】家づくり無料相談会(オンライン可)のご案内。費用や土地の悩み、何でもご相談ください」
「ネタ切れ」にならないためのネタの探し方
「カテゴリは分かったけど、やっぱりネタが続かない…」という方のために、ネタを探し続ける方法をご紹介します。
1. 「お客様の質問」はネタの宝庫
お客様から直接いただいた質問や、打ち合わせ中の会話こそが、最高のブログネタです。
一つのお客様の疑問は、まだ出会っていない他のお客様の疑問でもあります。
「先日、A様から『〇〇』とご質問いただいたので、ブログでお答えします!」という形で、そのまま記事にしましょう。
2. 「サジェストキーワード」からニーズを掘り起こす
Googleの検索窓に「〇〇市 注文住宅」と入れた時に、自動で表示される関連キーワード(例:「〇〇市 注文住宅 寒い」「〇〇市 注文住宅 後悔」「〇〇市 注文住宅 補助金」など)は、お客様の「生」の悩みそのものです。
3. 競合他社のブログを分析する
あなたの商圏で上位表示されている競合の工務店やリフォーム会社が、「どんな記事で」「どんなキーワードを」狙っているか分析しましょう。
注意: もちろんコピペは厳禁です。競合よりも「さらに詳しく、分かりやすく、自社の事例や想いを交えて」書くことが重要です。
SEOで評価される「読まれやすい記事」の書き方
最後に、記事の内容を検索エンジンと読者に正しく伝えるための、基本的な技術をご紹介します。
- 1記事1テーマの原則
- 例えば「耐震」と「断熱」について書きたい場合、1つの記事に詰め込まず、「耐震の記事」と「断熱の記事」に分けましょう。テーマを絞ることで、検索エンジンが「この記事は何についての記事か」を理解しやすくなります。
- タイトルと見出しの工夫
- タイトル(32文字以内目安): 検索キーワード(例:「工務店 ブログ」)と、可能であれば「地名」「お客様のメリット」を必ず入れます。
- 見出し(H2, H3タグ): 記事の「目次」の役割をします。見出しだけを読んでも内容がざっくり理解できるように、キーワードを自然に含めましょう。
- 画像や施工写真の活用
- 専門的な話が続く場合は、図解やグラフ(今回使用した表など)を入れ、視覚的に分かりやすくします。また、現場の作業風景や、スタッフの笑顔の写真 3 は、文字だけの記事よりも格段に信頼感を高めます。
- 内部リンクでサイトを回遊してもらう
- 記事の最後や、関連するトピックの途中に、他の記事へのリンク(内部リンク)を貼りましょう。
- (例)「耐震等級」の記事を読んだ人に、「当社の基礎工事のこだわり」の記事を案内する。
- (例)「お客様の声」の記事から、その方の「詳細な施工事例」の記事に誘導する。これにより、読者がサイト内を長く回遊してくれるため、SEOの評価向上に繋がります。
- 記事の最後や、関連するトピックの途中に、他の記事へのリンク(内部リンク)を貼りましょう。
- 更新頻度を保つ
- SEOにおいて、継続的な更新は重要です。完璧な記事を半年に1回書くよりも、80点の記事でも良いので定期的に(例:週に1回 5)更新し続けることが、結果としてサイト全体の評価を高めます。
まとめ

工務店のブログで何を書けばよいのかを、ご理解いただけたのではないでしょうか。
SEOは難しく聞こえるかもしれませんが、その本質は非常にシンプルです。
「あなたの地域(商圏)で、家づくりに悩んでいる『たった一人のお客様』の不安や疑問を、あなたの専門知識と誠実さで、誰よりも分かりやすく解決してあげること」
これに尽きます。
まずは完璧を目指さず、やれそうなことから始めてみましょう。
お客様からいただいた質問に1つ、ブログ記事で丁寧に答える。それだけでも、未来の別のお客様を助ける、素晴らしいコンテンツになります。
この記事が、貴社の素晴らしい技術と家づくりへの想いを、それを必要としている未来のお客様に届ける一助となれば幸いです。
貴社のブログ運営を、心から応援しています!
お問い合わせはこちら
当社ではホームページの制作と管理をおこなっています。
ホームページの管理費は月額換算で3,300円です(年払い税込39,600円)。
ホームページの管理をさせて頂いているお客様には、ブログ記事の書き方に関するご相談なども受けております。
これから作るホームページの制作、現在お持ちのホームページのリニューアルや保守管理に関してなど、ホームページに関することはなんでもお気軽にご相談ください。