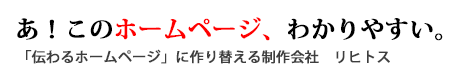目次
はじめに
クリニックのホームページは、体調に不安を抱えた患者さんが、最初にクリニックと接点を持つきっかけになります。
多くの場合、患者さんがクリニックに対して抱く第一印象は、このホームページによって決まります。
しかし、情報が探しにくかったり、必要な情報が不足していたり、あるいはデザインが古く信頼感に欠けていたりすることで、来院の機会を逃しているケースは少なくありません。
本記事は、クリニックを経営されている先生方に少しでも参考になればと思い、当社がクリニックのサイトの制作で注意している点を分かりやすくご紹介したいと思います。
なぜ「見やすいホームページ」が患者さん集患の鍵となるのか?

ホームページの見やすさが、なぜこれほどまでに重要視されるのでしょうか。
その答えは、不安を抱えた患者さんの心理と行動の中にあります。
患者さんがクリニックを探すプロセス
体調に異変を感じた患者さんの行動を想像してみましょう。
多くの場合、その旅はスマートフォンやパソコンでの検索から始まります。
例えば、「品川区 内科 土曜日」や「腰痛 整形外科」といった具体的なキーワードで検索し、表示された複数のクリニックのホームページを比較検討します。
このデジタル上の比較検討の段階で、患者さんは無意識のうちにクリニックを評価しています。
ホームページは「信頼性」を測るバロメーター
ホームページは、そのクリニックの専門性や患者さんへの配慮が伝わります。
デザインが乱れていたり、情報が探しにくかったりするサイトは、「実際の診療も整理されておらず、患者への配慮が足りないのではないか」という不安を無意識に抱かせてしまいます。
ホームページに求める情報がなかった場合、そのクリニックを選択肢から外すと回答する患者さんも多くいらっしゃいます。
単に「見やすい」というだけでなく、その先にある本質を理解することが重要です。
クリニックのホームページを訪れる患者さんは、単なるウェブサイトの閲覧者ではありません。
彼らは痛みや不安、焦りを抱え、助けを求めています。
このような精神状態では、複雑な情報を処理する認知的な余裕は普段よりも少なくなっています。
そこで、情報が煩雑で分かりにくいホームページに遭遇すると、患者さんのストレスはさらに増大します。
それは、助けを求めているまさにその瞬間に、新たな障壁にぶつかるようなものです。
一方で、構成が明快で、知りたい情報がすぐに見つかり、落ち着いたデザインのホームページは、患者さんの不安を積極的に和らげる効果があります。
それは、患者さんがクリニックのドアを開ける前から、そのクリニックの共感力と能力を静かに示していることに他なりません。
したがって、「見やすいホームページ」を設計することは、単なるマーケティング施策や技術的な作業なのではなく、患者さんへの配慮とケアをホームページで表現する作業なのです。
理想的な待合室が患者さんに安心感を与えるように、理想的なホームページもまた、訪れる人々の信頼を育むための重要な空間と言えます。
見やすいホームページの「7つの基本原則」
患者さんに信頼され、選ばれるホームページには、共通する普遍的な原則が存在します。
ここでは、その核となる「7つの基本原則」を、具体的な実践方法とともに解説します。
【原則1】患者さん最優先の情報設計
これは、患者さんが最も知りたい情報を、最も簡単に見つけられるようにウェブサイトを構造化することです。
体調が優れない中でサイトを訪れる患者さんは、サイトの隅々まで見て回る時間も気力もありません。
クリニックのホームページで最も閲覧されるページは、トップページ、医師紹介ページ、そしてアクセス情報のページという調査結果もあります。
具体的なやり方
クリニック名、住所、電話番号(スマートフォンではタップして電話がかけられる形式が望ましい)、そして「Web予約」や「お問い合わせ」といった行動を促すボタンなど、最も重要な情報をスクロールせずに表示される画面の最上部(ファーストビュー)に配置します。
これにより、患者さんは一目で基本的な情報を把握し、次の行動に移ることができます。
【原則2】清潔感と信頼感を伝えるビジュアル
ウェブサイトのデザインは、クリニックの品質や衛生観念に対する患者さんの認識に直接影響を与えます。
プロフェッショナルで、かつ温かみのある雰囲気を醸成することが重要です。
具体的なやり方
- 配色: 清潔感を象徴する白やライトグレーを基調とし、アクセントカラーとして信頼感や落ち着きを与える青、健康や安らぎを連想させる緑、あるいは親しみやすさを演出する温色系の柔らかい色合いを用いるのが効果的です。
- 写真: 汎用的な素材集の画像ではなく、プロのカメラマンが撮影した、実際の院内、設備、スタッフの高品質な写真を使用します。特に、医師の温和な笑顔の写真は、患者さんとの心理的な距離を縮め、信頼関係を築く上で非常に重要です。
- 余白(ホワイトスペース): レイアウトに十分な余白を設けることで、すっきりとして落ち着いた、現代的な印象を与えます。これにより、情報が整理され、可読性が向上し、患者さんは重要なコンテンツに集中しやすくなります。
【原則3】直感的なレイアウトとナビゲーション
患者さんがサイト内で迷子になることなく、数回のクリックで目的の情報にたどり着ける、論理的で一貫性のあるサイト構造を指します。
分かりにくいナビゲーションは、患者さんの不満の主な原因となり、サイトからの離脱に直結します。
具体的なやり方
メインメニューの項目は「診療案内」「医師紹介」「アクセス」など、誰にでも理解できる簡潔な言葉で構成します。
どのページを閲覧していても、必ずトップページに戻れるリンクを配置することが推奨されています。
予約ボタンのような重要な機能は、ヘッダーに固定表示するなど、常に目立つ場所に一貫して配置することで、患者さんの利便性を高めます。
【原則4】文字の読みやすさ
年齢や視力の状態に関わらず、すべてのユーザーがテキストを容易に読めるようにすることです。
小さな文字が密集した文章は、特に高齢の患者さんや視覚に制約のある方にとって、大きな障壁となります。
具体的なやり方
- フォント: 画面上での視認性が高い、ゴシック体のようなシンプルでクリーンなフォントを選びます。装飾過多なフォントは避けるべきです。
- サイズとコントラスト: 十分な文字サイズを確保し、テキストと背景の間に高いコントラスト(例:白い背景に黒い文字)を持たせることが、日本医師会のガイドラインでも推奨されています。
- 書式設定: 長い文章は、適切な見出しや箇条書き、短い段落で区切ることで、視覚的に情報を整理し、読みやすさを向上させます。
【原則5】スマートフォン完全対応(レスポンシブデザイン)
パソコンの大きな画面からスマートフォンの小さな画面まで、あらゆるデバイスのサイズに合わせて表示が自動的に最適化されるデザインのことです。
現代の患者さんの多くは、スマートフォンを使ってクリニックを検索します。
スマートフォンに対応していないサイトは、この膨大な数の潜在患者に対して、大きな機会損失になる可能性があります。
さらに、検索エンジンであるGoogleも、検索順位を決定する際にモバイル対応サイトを優先する「モバイルファーストインデックス」を採用しており、SEOの観点からも必須の要件となっています。
これは、ウェブサイト制作の初期段階から組み込むべき技術標準です。
【原則6】専門用語を避けた分かりやすい言葉
医療に関する専門的な内容を、一般の患者さんが理解できる平易な言葉で説明することです。
難解な専門用語は、患者さんの理解を妨げ、不安を増大させる壁となります。
具体的なやり方
常に患者さんの視点に立って文章を作成します。
専門用語の使用が避けられない場合は、直後に括弧書きで簡単な説明を加える(例:「除脈(脈拍が少ない状態)」)などの配慮が必要です。
また、複雑な概念は、イラストや図を効果的に用いて視覚的に説明することで、理解を助けることができます。
【原則7】ユニバーサルアクセシビリティ
これは、視覚、聴覚、運動機能などに障害を持つ人々を含め、誰もがウェブサイトを利用できるように設計することです。
これは医療の基本理念とも合致する倫理的な責務であり、地域社会のすべての人々が重要な健康情報にアクセスできることを保証します。
具体的なやり方
日本医師会のガイドラインなどに示されている指針に従います。
具体的には、画像に代替テキスト(alt属性)を設定してスクリーンリーダーが内容を読み上げられるようにしたり、キーボード操作だけでサイト内を移動できるようにしたり、色の違いだけに頼らずに情報を伝える工夫などが含まれます。
患者さんが本当に求めている情報とは?

効果的なホームページを構築するためには、これらの基本原則に基づき、患者さんが実際に求めている情報を的確に提供する必要があります。
患者さんのニーズは、突き詰めると2つの根源的な問いに集約されます。
それは「そこへ行くことができるか?(実用性の確認)」と「そこを信頼できるか?(安心感の確認)」です。
患者さんの行動データ分析からも、この傾向は明らかです。
アクセスや診療時間といった実用的な情報と、医師のプロフィールや院内の雰囲気といった信頼性に関わる情報が、常に高い関心を集めています。
この2つの軸を意識してコンテンツを整理することで、患者さんの根本的なニーズに応えるホームページを構築できます。
以下のチェックリストは、この考え方に基づき、クリニックのホームページに不可欠なコンテンツを網羅したものです。
自院のサイトに不足している情報がないか、確認してみましょう。
表1:クリニックホームページ必須コンテンツチェックリスト
| コンテンツ項目 | 掲載すべき内容 | なぜ重要か (患者さんの視点) |
| 【実用性情報】 | ||
| 診療時間・休診日 | 表やカレンダー形式で分かりやすく表示。急な休診情報はトップページで目立つように。土日や夜間診療は大きなアピールポイント。 | 「私のスケジュールで行けるだろうか?」仕事や家庭の都合と合うか、すぐに確認したい。 |
| アクセス・連絡先 | 住所、電話番号、Googleマップの埋め込み。最寄り駅からの写真付きルート案内、駐車場の有無と台数。 | 「迷わずたどり着けるだろうか?」初めての場所は不安。分かりやすい地図と目印になる外観写真があると安心できる。 |
| 診療科目・対応症状 | 診療科目の一覧だけでなく、「こんな症状の方へ」といった形で、具体的な症状から探せるようにする。 | 「私のこの症状は、ここで診てもらえるのだろうか?」専門用語の羅列ではなく、自分の悩みに直結する言葉で書かれていると分かりやすい。 |
| 【信頼性情報】 | ||
| 医師・スタッフ紹介 | 院長の顔写真(笑顔で明るいもの)、経歴、専門資格、所属学会、治療方針や患者さんへのメッセージ。 | 「どんな先生だろう?信頼できる人だろうか?」治療を受ける上で最も重要。人柄や考え方が伝わると、安心して相談できる。 |
| 院内の雰囲気・設備紹介 | 待合室、診察室、受付、医療機器などの鮮明な写真や動画。清潔感や衛生管理への取り組みを伝える。 | 「クリニックは清潔だろうか?怖い場所じゃないだろうか?」院内の雰囲気が事前に分かると、来院時の緊張が和らぐ。 |
| 診療方針・クリニックの理念 | なぜこの地で開業したのか、どのような医療を目指しているのか。クリニックの「想い」を伝える。 | 「このクリニックは、自分と考え方が合うだろうか?」治療への姿勢や価値観に共感できると、より深い信頼関係を築ける。 |
| 治療内容・料金 | 特に自由診療の場合は、治療の流れ、リスク、副作用、料金表(税込/税別を明記)を詳しく掲載。 | 「どんな治療をされるんだろう?費用はいくらかかるんだろう?」治療内容と費用の透明性は、不安を解消し、信頼につながる。 |
| 【利便性・その他】 | ||
| 予約システム | 24時間受付可能なWeb予約フォームへの分かりやすいリンク。予約方法の流れを説明。 | 「電話する時間がない」「すぐに予約したい」Webで簡単に予約できると、受診のハードルがぐっと下がる。 |
| お知らせ・ブログ | 休診情報、季節の健康情報、新しい治療の紹介など。定期的な更新が重要。 | 「このクリニックはちゃんと運営されているだろうか?」情報が常に新しいと、活気があり信頼できるクリニックだと感じる。 |
SEOで上位表示を狙うための専門的アプローチ

「見やすい」ホームページを構築しても、患者さんに見つけてもらえなければ意味がありません。
ここで重要になるのが、SEO(検索エンジン最適化)です。
特にクリニックのホームページにとって、SEOは単なるマーケティング技術ではありません。
それは、自院の専門的な信頼性を、検索エンジンが理解できる言語に翻訳するプロセスです。
医療情報は、Googleによって「YMYL(Your Money or Your Life)」、つまり人々の幸福、健康、経済的安定、安全に大きな影響を与える可能性のある分野に分類されています。
そのため、Googleは医療関連のコンテンツを極めて厳格な基準で評価します。
この評価基準こそが「E-E-A-T」です。(※E-E-A-Tに関しましては『E-E-A-Tとは』のページでもご説明していますので、ご参照下さい。)
E-E-A-Tを満たすための施策は、倫理的な医療行為の原則と深く結びついており、医師にとっては直感的に理解しやすいはずです。
キーワード戦略:患者さんが使う言葉で考える
SEOの第一歩は、患者さんがどのような言葉で検索するかを理解することです。
- 地域名(ローカル)キーワード: クリニックにとって最も重要なキーワードです。「地域名 + 診療科目」(例:「渋谷区 皮膚科」)や「地域名 + 診療科目 + 特徴」(例:「品川区 内科 土曜日」)といった組み合わせを意識して、ホームページのタイトルや見出し、本文に自然な形で盛り込みます。
- 症状・疾患名キーワード: 患者さんは具体的な症状で検索することも多いため、「症状名 + 診療科」(例:「腰痛 整形外科」)や「疾患名 + 治療」といったキーワードも重要です。
- お悩み(ロングテール)キーワード: より具体的で複数の単語からなる検索語句(例:「〇〇の治療が得意なクリニック」「オンライン診療 予約方法」)は、検索ボリュームは少なくても、来院意欲が非常に高い患者さんを捉えることができます。
E-E-A-T:Googleから「信頼できる」と評価されるための最重要要素
E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取ったものです。
これら4つの要素を高めることが、YMYL分野である医療サイトのSEO成功の鍵となります。
Experience(経験)
コンテンツが、そのトピックに関する実際の経験や体験に基づいて書かれているかを示します。
- 実践方法: 院長や医師が実際に経験した症例(個人情報保護に最大限配慮した上で)や、クリニックで実際に行っている治療法に関する詳細な解説、臨床での観察に基づいたコラムなどを掲載します。一次情報、つまり自院ならではの独自の情報を発信することが価値を高めます。
Expertise(専門性)
コンテンツの作成者が、その分野の専門家であることを示します。
- 実践方法: 健康や疾患に関するすべての記事は、必ず資格を持つ医師が執筆、または監修(監修者名を明記)するようにします。著者(監修者)のプロフィールページを設け、経歴、専門医・指導医資格、所属学会、論文発表歴などを詳細に記載することが極めて重要です。
Authoritativeness(権威性)
コンテンツの作成者やウェブサイトが、その分野における権威として広く認知されているかを示します。
- 実践方法:
- 情報源の明記: 記事内で言及する医学的根拠については、厚生労働省のガイドライン、関連学会の診療指針、権威ある医学論文など、信頼できる情報源へのリンクや出典を明記します。
- 被リンクの獲得: 地域の医師会、連携している基幹病院、公的な医療情報サイトなど、権威のあるサイトから自院のホームページへリンクを張ってもらうことは、権威性の証明として非常に効果的です。
- 実績のアピール: 学会での登壇歴、メディアでの掲載歴、受賞歴なども権威性を示す要素となります。
Trustworthiness(信頼性)
ウェブサイトとその運営者が、誠実で信頼に足る存在であることを示します。
- 実践方法:
- 運営者情報の明記: クリニックの正式名称、住所、電話番号(NAP情報と呼ばれ、各種媒体で統一することが重要)をフッターなどに明確に表示します 23。プライバシーポリシーやお問い合わせフォームも必須です。
- SSL化: ウェブサイトの通信を暗号化するSSL(URLが「https://」で始まる)は、セキュリティの基本であり、信頼性の証です。これが導入されていないサイトは、ブラウザに「保護されていない通信」と表示され、患者さんに不安を与えます。
- 情報の最新性: 診療時間や休診日、提供サービスなどの情報は、常に正確かつ最新の状態に保つ必要があります。古い情報が放置されているサイトは信頼を失います。
【要注意】医療広告ガイドライン遵守のポイント

クリニックのホームページを運営する上で、絶対に避けては通れないのが「医療広告ガイドライン」です。
ここでまず理解すべき最も重要な点は、クリニックのホームページは、法律上「広告」とみなされるということです。
かつて存在した比較的緩やかな「医療機関ホームページガイドライン」は廃止され、より厳格な「医療広告ガイドライン」に統合されました。
このガイドラインは、不当な表示によって患者さんが不利益を被ることを防ぎ、適切な医療選択を支援することを目的としています。
したがって、ガイドラインを遵守することは、単なる法的な義務を果たすだけでなく、クリニックの倫理観と誠実さを示す行為であり、患者さんからの信頼を築くための土台そのものです。
ガイドラインは複雑ですが、特に注意すべきポイントを、具体的なOK例・NG例と共に以下の表にまとめました。
自院のサイトが抵触していないか、チェックしてください。
表2:医療広告ガイドライン:「OKな表現」と「NGな表現」の比較
| 項目 | 禁止される表現 (NG例) | 許容される表現 (OK例) | ガイドラインの根拠 |
| 比較優良広告 | 「地域No.1の実績」「日本一の専門医」 | 「〇〇駅から徒歩1分」「〇〇の治療に力を入れています」 | 他院と比較して自院が優れていると示す客観的な事実がない表現は禁止 |
| 誇大広告 | 「絶対に治ります」「100%安全な手術です」 | 「治療効果には個人差があります」「治療の主なリスクとして〇〇があります」 | 治療の効果や安全性を保証するような、事実を誇張した表現は禁止 |
| 患者の体験談 | 「〇〇さんの声:先生のおかげですっかり良くなりました!」 | (原則として掲載不可) | 患者個人の主観や伝聞に基づく体験談は、内容を問わず禁止 |
| ビフォーアフター写真 | 写真のみを並べて劇的な変化を強調する。 | 通常の診療範囲、治療内容、費用、主なリスク、副作用などの詳細な説明を併記する。(限定解除要件を満たす必要あり) | 患者を誤認させるおそれがあるため、掲載には厳しい条件が付されている |
| 費用 | 「今だけキャンペーン価格!」(期間や条件の明記なし) | 「自由診療の〇〇は、費用〇〇円(税込)です。詳細は料金ページをご覧ください。」 | 費用を強調して誘引したり、誤解を招く表現は禁止。自費診療は料金の明記が必須 |
まとめ

「見やすい」クリニックのホームページ作りは、単なる集患のためのテクニックではない、ということをご理解いただけたのではないかと思います。
「見やすい」クリニックのホームページ作りは、患者さんへの配慮とケアを表現する作業です。
ホームページは、不安を抱えた患者さんが、あなたのクリニックに初めて触れる場所です。
その場所が、分かりやすく、信頼できる空間であれば、患者さんは安心して次のステップに進むことができます。
患者さんから「見やすい」「分かりやすい」と感じていただけるだけでなく、「このクリニックなら信頼できる」と安心して来院を決めていただけるようなホームページを制作・改善するために、少しでも参考になれれば幸いです。